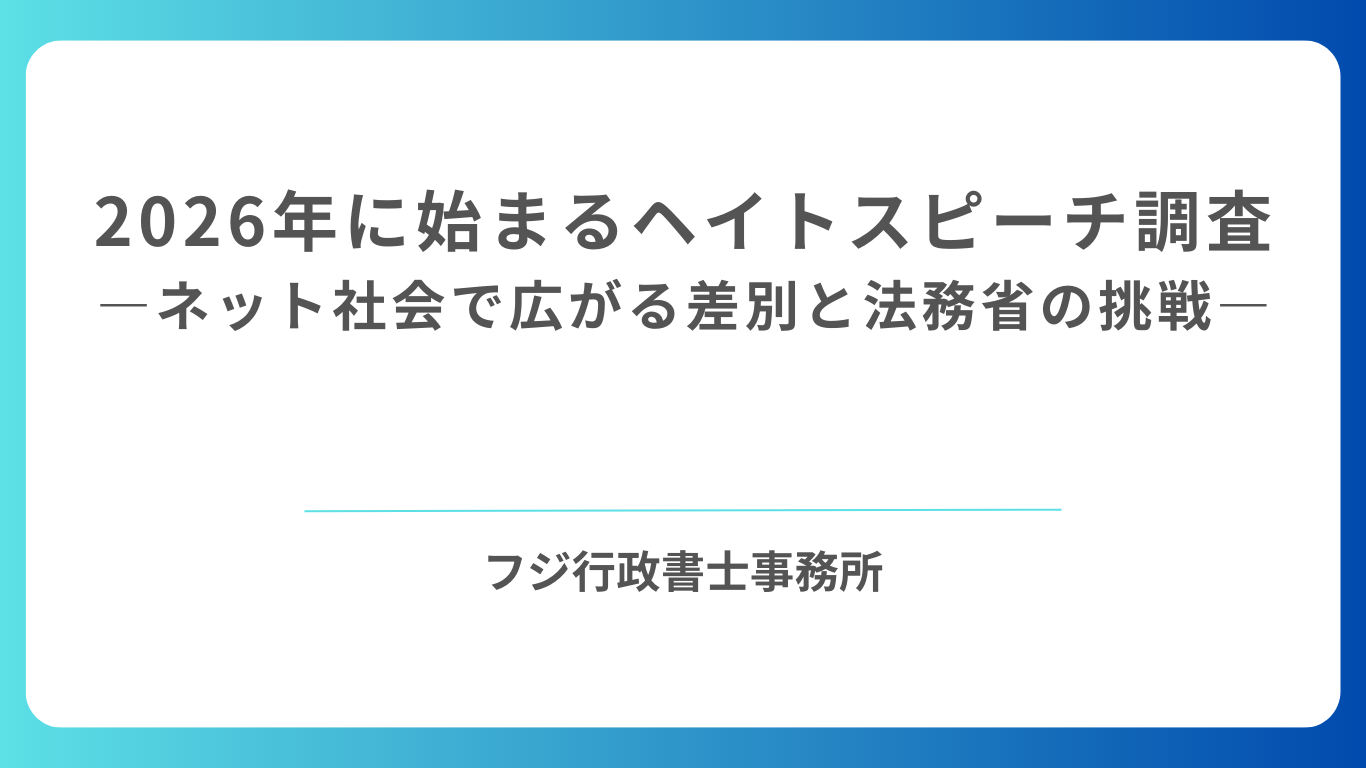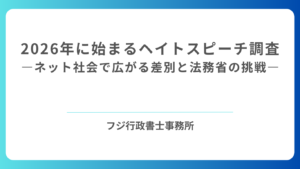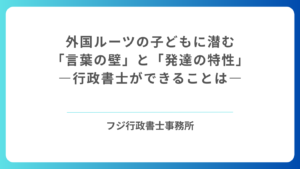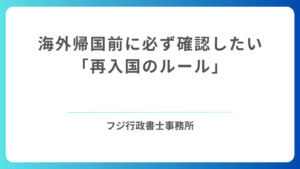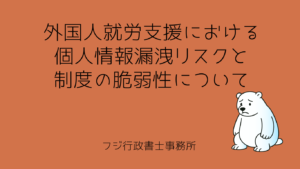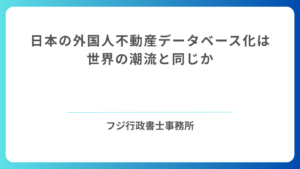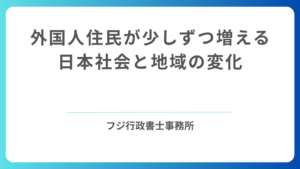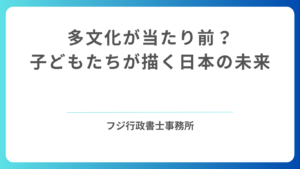法務省が進める2026年度ヘイトスピーチ調査――浮かび上がる社会の課題
法務省が調査に踏み切る理由
法務省は2026年度から、ヘイトスピーチの現状を明らかにするための調査を始める方針を固めました。差別をあおる発言や排外的なスローガンは、これまで街頭でのデモ活動を通じて注目されてきましたが、近年はSNSやインターネット掲示板を中心に拡散しています。誰もが手軽に情報発信できる環境が整ったことで、こうした言動の影響力は格段に大きくなっています。
2010年代には在日コリアンを狙った差別的な街頭活動が全国で問題視されました。その後、2016年には「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、差別を許さないという理念が国として打ち出されました。しかし法律自体には罰則が設けられていないため、実効性には限界があると指摘されています。解消法施行から10年という節目を迎えるにあたり、政策の検証と新たな方向性を探る必要があるのです。
SNSで広がる排外的言動
近年の大きな変化は、差別の場が「街頭」から「オンライン」へ移ったことです。街頭デモは減少傾向にある一方で、匿名性の高いSNSや掲示板では差別的な書き込みが目立つようになっています。投稿は短時間で拡散し、消去が難しいため、被害が広範囲に及びやすいという特徴があります。
さらに、攻撃の対象も広がっています。これまで主に在日コリアンが標的とされてきましたが、近年はクルド人をはじめ、地域に暮らす他の外国人住民も差別の矢面に立たされています。根拠のない偏見による言葉の暴力は、共生社会の実現を妨げる大きな壁となっています。こうした状況を把握するため、法務省は調査費用として約7,000万円を概算要求に盛り込みました。
調査が持つ意味
今回の調査は単に数字を集めることが目的ではありません。第一に、政策の効果を検証する役割を担っています。街頭でのデモが減ったのは社会的な批判や制度の効果なのか、それとも活動の場がインターネットに移っただけなのかを確認する必要があります。
第二に、多様化する差別の対象を明らかにすることです。どのような外国人コミュニティが被害を受けているのかを具体的に示すことで、支援策を設計しやすくなります。
第三に、制度や法律を見直す際の基礎資料となります。解消法の限界を踏まえ、罰則の導入や啓発活動の強化、相談窓口の拡充など、より実効性のある対応につなげることが期待されます。
そして、この調査自体が「差別を許さない」という国の姿勢を明確に示す意味を持っています。社会に向けた強いメッセージは、抑止効果や啓発効果につながるでしょう。
今後の課題と市民の役割
ただし、調査を行うだけで差別がなくなるわけではありません。むしろ、現状を明らかにすることで新たな課題が見えてくるはずです。特に、ネット上の差別的な発言をどう扱うかは難しい問題です。表現の自由とのバランスを取りながら、プラットフォーム運営者との協力や教育啓発を通じて改善を図る必要があります。
また、被害を受けた人々が安心して相談できる環境を整えることも欠かせません。心理的なケアや法的な支援体制を強化することで、孤立を防ぐことができます。行政だけでなく、地域社会や市民団体、専門家が協力して取り組むことが重要です。
さらに、市民一人ひとりの意識も問われています。SNSで差別的な投稿を見たときに無関心でいないこと、偏見に左右されず正しい情報を理解しようと努めること。こうした小さな行動の積み重ねが、社会全体の雰囲気を変えていきます。
2026年度に予定されている実態調査は、日本社会が今後どのように共生を実現していくかを考える出発点です。差別のない社会を築くためには、国の施策だけでなく、市民一人ひとりの姿勢が大きな意味を持ちます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。