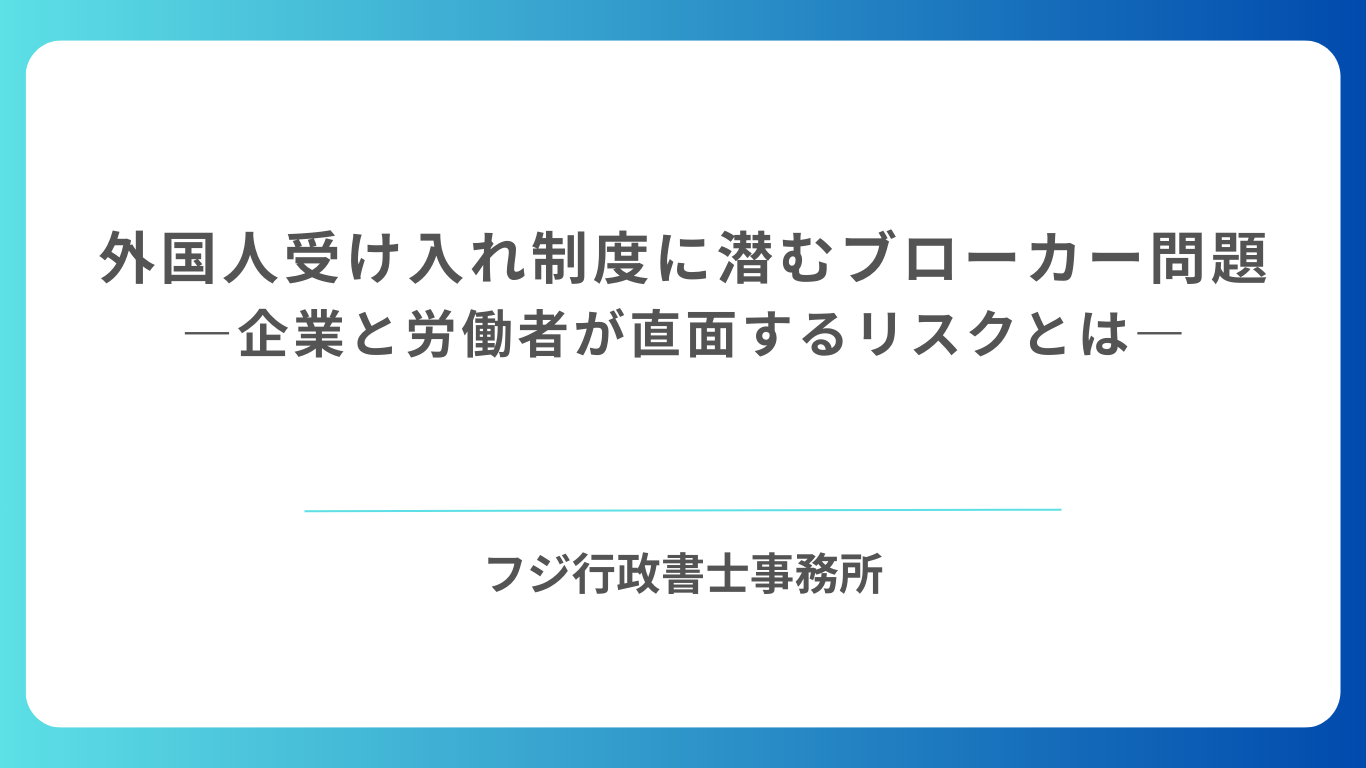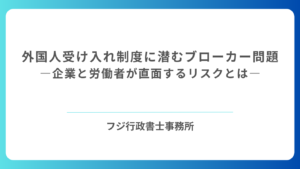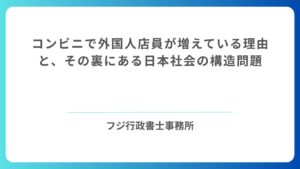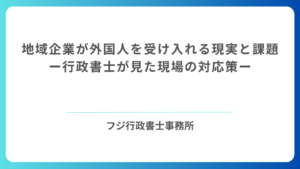制度の理想と現実
日本の労働市場は慢性的な人手不足に直面しています。その解決策として導入されたのが、外国人材を受け入れる各種制度です。技能実習や特定技能といった在留資格は、単に労働力を補うだけでなく、外国人が日本で経験を積み、知識や技術を習得する場としての役割も担っています。特定技能については、試験を通過した人材を人手不足分野に迎え入れるという建前があり、制度自体の設計は理にかなっています。
ところが、実際の運用は必ずしも理想通りにはいきません。制度の規定は複雑で、外国人労働者にとっても、受け入れる企業にとっても理解が難しい部分が多々あります。その隙間を埋める存在が仲介業者や支援機関ですが、中にはその立場を利用して不適切な利益を上げる例も見られます。結果として、「制度が存在するのに遵守されない」「理念が形骸化している」といった矛盾が目立つようになっています。
ブローカーが入り込む背景
こうした問題が生じるのには理由があります。
まず、企業側の事情です。人手不足に悩む職場では「誰でもいいから働き手が欲しい」という切実な思いが先行し、制度の細部にまで注意を払う余裕がないのが実情です。そのため、制度に詳しいとされる仲介者に頼る流れが生まれます。
一方で、外国人労働者自身も制度への理解が十分とは言えません。言語の壁や法律知識の不足により、「この仕事なら大丈夫」と言われれば受け入れてしまうことが多く、生活を維持するために疑問を持ちながらも従わざるを得ない状況に陥ります。
さらに仲介者の側面です。支援機関や派遣業者の中には、制度の監視が十分でない点を逆手に取り、企業から紹介料を得たり、外国人から管理費を徴収したりすることで利益を重ねる例があります。結果的に、企業と外国人の双方から収益を得る構造が形成され、ブローカー的存在が活動しやすい環境ができあがっているのです。
現場で起こりやすい問題
こうした構図のもとで実際に起こる問題は多岐にわたります。
最も代表的なのは、在留資格で認められていない業務に従事させることです。本来は分野ごとに明確な制限があるにもかかわらず、人手不足や業務上の都合で資格外の仕事をさせてしまうケースが見られます。これは外国人本人にとって在留資格の取り消しリスクを伴い、企業にとっても法的責任を問われる可能性があります。
次に、金銭的な負担です。「支援費」や「管理費」といった名目で不透明な費用が課されることがあります。外国人は相場を知らないため、過剰な金額でも受け入れてしまい、借金や生活苦に追い込まれる例が後を絶ちません。
また、労働環境の悪化も見逃せません。制度に沿わない人材活用は契約内容が曖昧で、残業代未払い、休日が取れないといった事態につながります。表向きは「支援」としていても、実態は搾取に近い状況が生じることがあります。
これらの問題は外国人労働者だけでなく、企業にとっても大きなリスクです。違反が発覚すれば信用失墜や処分、場合によっては刑事責任を問われる可能性があり、短期的には人材を確保できても、長期的には経営に深刻な影響を与えかねません。
改善に向けた視点
問題を未然に防ぐには、いくつかの取り組みが必要です。
まず、制度の監督機能を強化することです。技能実習制度では監理団体が検査対象となりますが、特定技能の支援機関は登録制のためチェックが十分に及んでいません。今後は実効性のある監査体制を整えることが求められます。
次に、企業の意識改革です。人材不足を理由に仲介業者へ丸投げするのではなく、制度のルールを理解し、自ら責任を持って受け入れる姿勢が必要です。安易な依存は、企業自身にとって大きなリスクを招きます。
加えて、外国人への情報提供も不可欠です。母国語での案内や相談窓口を充実させることで、自分の資格でどのような業務ができるのかを理解しやすくし、不当な労働を防ぐ環境を整えることができます。
最後に、受け入れの発想そのものを見直すことです。「安価な労働力確保」という短期的な視点ではなく、「安心して長く働ける環境づくり」が企業の成長につながるという認識が必要です。制度の理念を守ることこそが、結果的に双方に利益をもたらすのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。