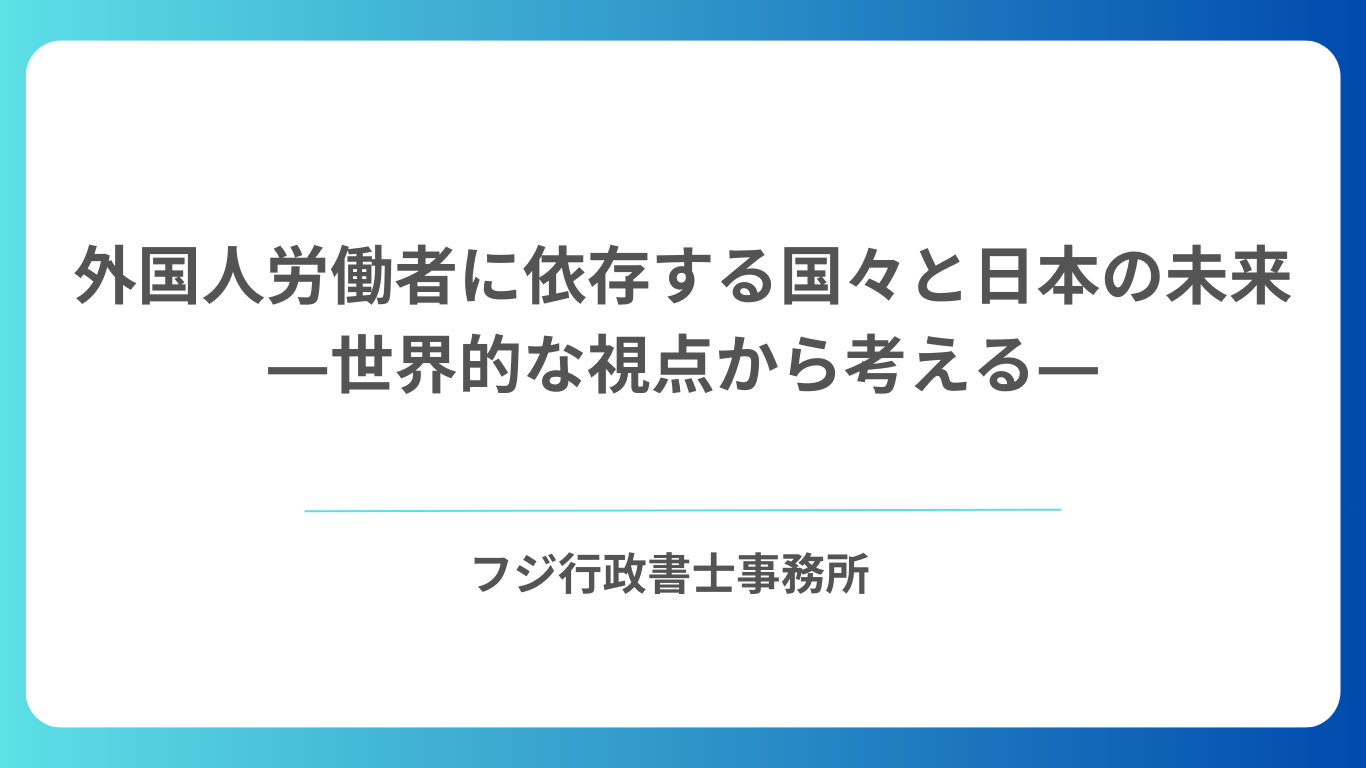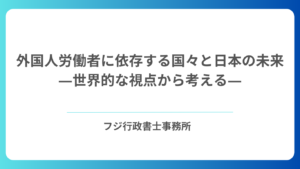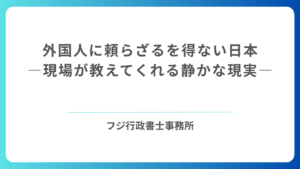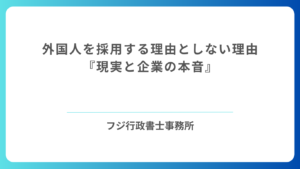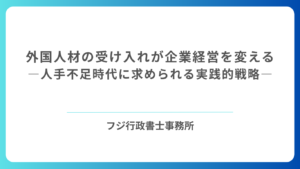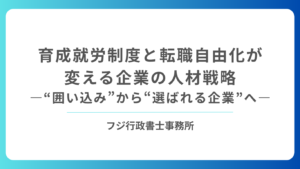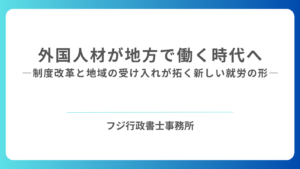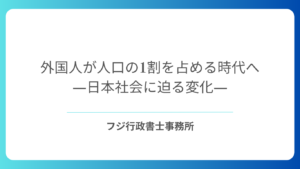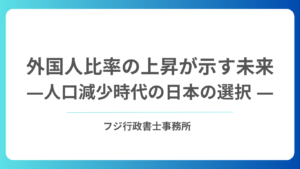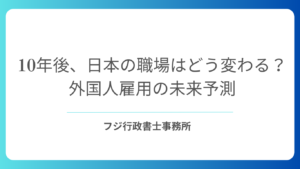日本の外国人労働者依存の現状
近年、日本社会は深刻な人手不足に直面しており、その不足を補う存在として外国人労働者が不可欠な役割を担っています。特に介護や建設、農業、製造業といった分野では、日本人労働者の確保が難しく、外国人が現場を支える実態が広がっています。法務省の統計によれば、外国人労働者数は年々増加し、今や170万人を超える規模となりました。これは単なる一時的な現象ではなく、長期的な人口減少のなかで不可避の流れといえます。政府は「技能実習」や「特定技能」といった在留資格を整備し、受け入れ制度を制度化していますが、制度の複雑さや権利保護の不十分さが課題として残ります。例えば技能実習制度では、建前上は「技能移転」とされていますが、実態は労働力確保が目的となっており、労働環境の改善や社会統合が遅れていると指摘されています。今後、日本が真に持続可能な労働力供給を実現するためには、単なる数合わせの政策ではなく、外国人が安心して働き暮らせる基盤を築くことが重要になります。
中国と日本の比較
日本とよく比較されるのが中国です。中国は世界最大の人口を誇りますが、都市部の経済発展が進むにつれて、地方から都市への出稼ぎ労働者の役割が重要となりました。かつては国内労働力のみで産業を支えてきましたが、近年は出生率の低下や高齢化が進み、労働力人口そのものが減少傾向にあります。こうした背景から、中国は外国人労働者の受け入れを少しずつ拡大し始めています。ただし、日本ほど明確な制度化はされておらず、まだ試験的な段階にとどまっています。日本が既に外国人依存を社会全体に広げているのに対し、中国は自国民の移動によって労働市場を維持している点が大きな違いです。今後、経済成長の鈍化と人口減少が進むなかで、中国も日本同様に「外国人をどのように受け入れるか」という課題に直面することは避けられないでしょう。両国を比較すると、日本はすでに制度と現場の矛盾が露呈しているのに対し、中国は制度化をどう進めるかという段階にあるといえます。
世界に広がる外国人依存の動き
日本や中国だけでなく、世界各国が労働力不足を背景に外国人労働者への依存を深めています。たとえばドイツは、トルコや東欧諸国から多くの移民を受け入れ、社会制度のなかで統合政策を進めてきました。カナダやオーストラリアは移民国家として、積極的に高度人材を呼び込みつつ、生活基盤の支援も行っています。中東の産油国では、自国民の多くが公務員やホワイトカラーに従事し、労働市場の大半を外国人が担っています。これらの国々に共通するのは、労働力の補填にとどまらず、外国人を社会の一部としてどのように位置づけるかに課題が移っている点です。日本はこの点で大きく遅れをとっており、単に「働き手」として受け入れるだけでなく、教育・住宅・地域交流といった生活基盤を含めた総合的な政策を進める必要があります。世界の事例を参考にしながら、自国に合った受け入れモデルを構築することが今後の鍵となるでしょう。
これからの日本の選択肢
今後、日本は「外国人労働者をどう受け入れるか」という問いに真正面から向き合わなければなりません。現状のままでは、人手不足を補うために外国人を増やしつつも、社会統合や教育支援が不十分なまま矛盾が拡大していく可能性があります。一方で、受け入れ体制を抜本的に改革し、外国人が地域社会の一員として安心して暮らせる仕組みを整えれば、日本社会は多文化共生のモデルへと進化できるでしょう。たとえば地方都市での外国人住民の増加は、人口減少に悩む地域に新しい活力をもたらす可能性を秘めています。教育機関が外国人子女に支援を強化し、地域住民との交流が深まれば、単なる「労働力」ではなく「共に未来を築く仲間」として位置づけられるはずです。政策選択は簡単ではありませんが、今こそ「労働力不足の解決」と「社会の持続性」を両立させるためのビジョンが問われています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。