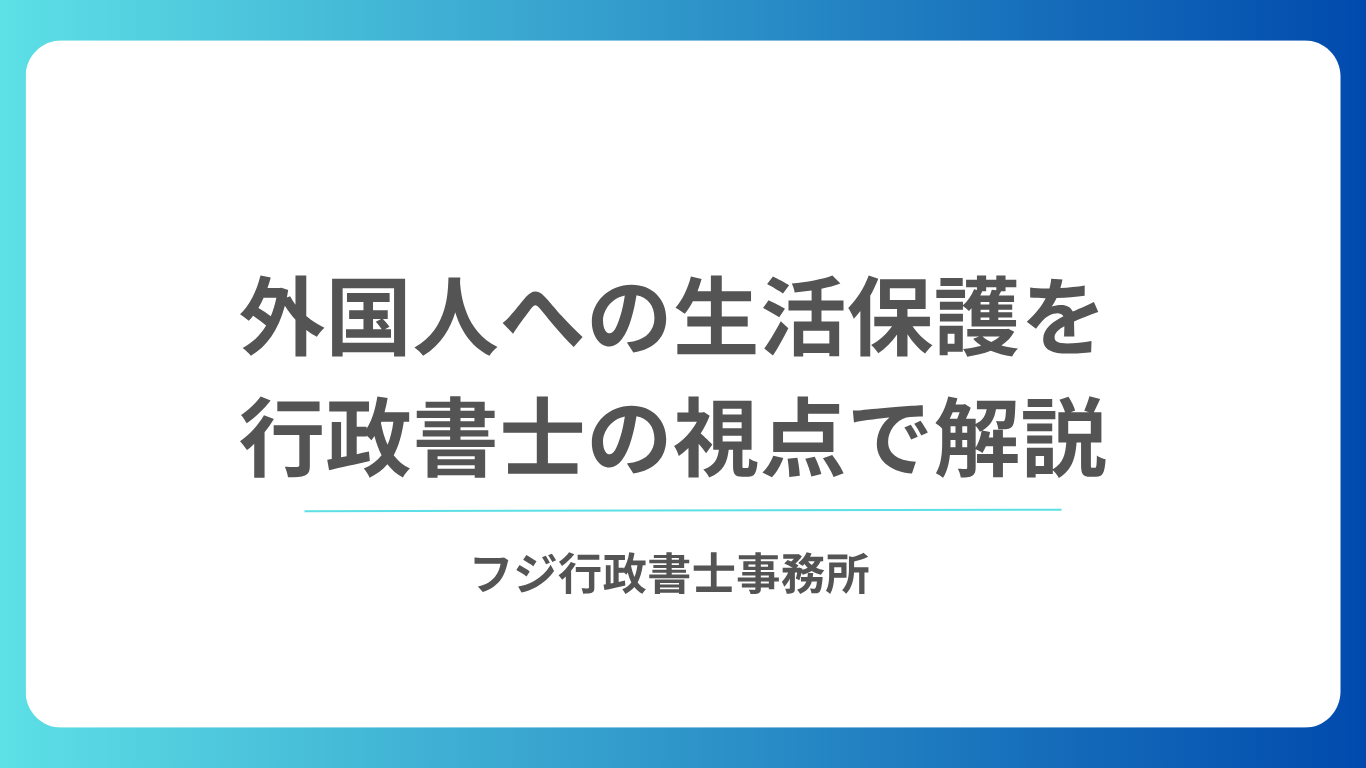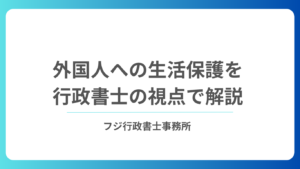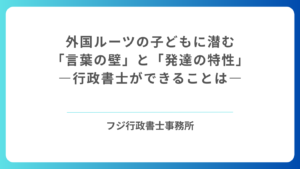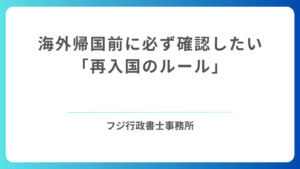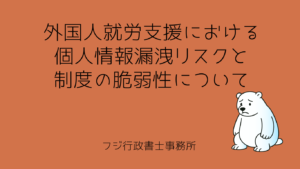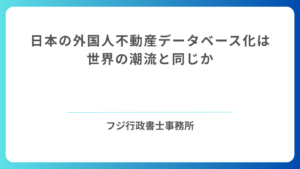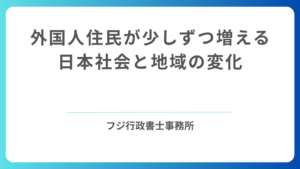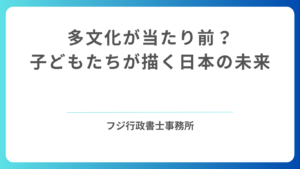外国人と生活保護制度の概要
日本の生活保護制度は、憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための仕組みです。本来は日本国民を対象にした制度ですが、戦後の運用や国の通知により、一定の条件を満たす外国人にも適用される場合があります。具体的には、日本に中長期的に在留し、永住者や定住者、日本人の配偶者等といった安定した在留資格を持つ外国人が、やむを得ず生活に困窮した場合に申請の対象となります。
ただし、法律の条文に「外国人も対象」と明記されているわけではなく、あくまで自治体が日本人と同様の基準で準用しているのが実態です。そのため、地域によって運用の細部が異なることもあります。申請を行う際には、収入や資産、扶養義務者の有無などが厳しく確認され、日本人と同じく生活状況を詳細に審査されます。
外国人が生活保護を申請できる条件
外国人が生活保護を受けるには、まず安定した在留資格が必要です。短期滞在や就労資格のない在留資格では原則として対象外です。また、日本での生活基盤があり、ほかに収入や扶養してくれる家族がいないことが条件となります。
たとえば、永住者や定住者、日本人配偶者であっても、勤務先の倒産や病気、事故などで生活が成り立たなくなった場合は申請の対象になります。ただし、生活保護は「最後のセーフティネット」であるため、申請の前に貯金や所有する不動産などの資産は生活費に充てることを求められます。さらに、働ける年齢や健康状態であれば就労活動を行う義務があります。自治体は外国人だから特別扱いするわけではなく、日本人と同じ基準で、生活の立て直しに向けた努力が求められます。
社会の反応と誤解
外国人の生活保護受給は、ニュースやSNSなどで話題になることがあり、賛否が分かれます。「税金はまず日本人のために使うべきだ」という意見もあれば、「長年日本で暮らし社会に貢献してきた外国人にも保障は必要だ」という意見もあります。
一部では「外国人は簡単に生活保護を受けられる」という誤解がありますが、実際には日本人と同じく厳しい審査が行われています。申請者の収入や資産、扶養状況を細かく確認し、不正受給を防ぐための調査も徹底されます。また、外国人受給者の多くは長年日本で働き、納税し、地域社会に関わってきた人たちです。事実を無視して感情的な批判だけが先行すると、制度の目的や人道的な意味が見えにくくなります。大切なのは、事実に基づいて冷静に議論することです。
制度運用の課題と行政書士としての経験
外国人の生活保護受給には、制度上の課題も存在します。まず、法律上は「準用」という形での適用であり、法的な位置づけが明確ではありません。今後の法改正や方針の変更によって、対象範囲や運用が変わる可能性もあります。また、自治体によって外国人対応の経験や通訳体制に差があり、申請時に十分な説明が受けられず誤解が生じることもあります。さらに、外国人の場合は母国との送金や扶養関係など、確認すべき事項が日本人よりも複雑です。
私は行政書士として、外国人の在留資格や永住申請をサポートする中で、生活保護の受給が将来の在留資格審査に影響する場面を見てきました。そのため、依頼者には生活保護制度の仕組みや申請手順だけでなく、受給後の生活設計や在留資格への影響まで含めて説明するようにしています。生活保護に関する誤解や偏見を減らし、本当に必要な人が必要な支援を受けられるよう、制度と現場をつなぐ役割をこれからも果たしていきたいと考えています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。