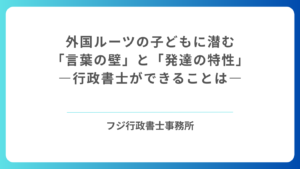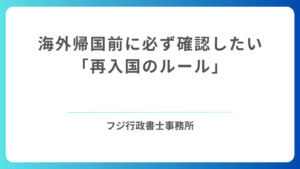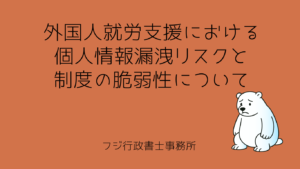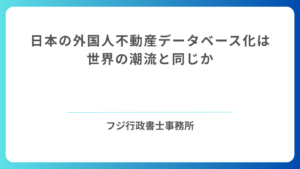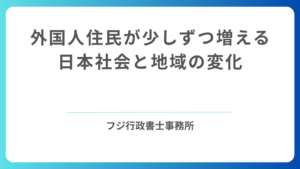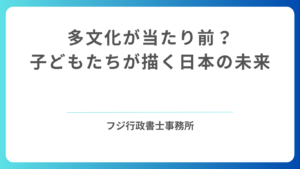「うちの子、本当に学校に行けるのだろうか?」
そんな不安を、誰にも相談できずに抱える外国人の親がいます。入学案内が届かない。届いても日本語だけで読めない。何を準備すればいいか分からない。役所に行っても、どの窓口に行けばよいかも分からない。そんな“はじめの一歩”の時点で立ち止まってしまう家庭が、今も現実に存在しています。
“Will my child really be able to go to school?”
Many foreign parents in Japan carry this fear without knowing where to turn. Enrollment documents don’t arrive—or if they do, they’re only in Japanese. They don’t know what to prepare or which government office to visit. At this very first step, families become stuck. And this still happens today.
制度があっても、それだけでは足りない
日本の公立小学校は、原則として外国人の子どもも受け入れています。ですが、それは“制度上可能”というだけで、実際に入学までたどり着けない家庭も少なくありません。文部科学省の調査によれば、2023年時点で学齢期にありながら学校に通っていない外国籍の子どもは全国で8,600人以上。制度はあっても、情報が届かなければ、意味を成さないのです。
In principle, Japan’s public elementary schools accept foreign children. But just because it’s “technically possible” doesn’t mean it’s happening. A 2023 survey by the Ministry of Education showed over 8,600 school-age foreign children were not attending school. If the system exists but the information doesn’t reach families, it’s as good as useless.
「わからなかったから行かなかった」
実際に多くの不就学ケースでは、保護者が「制度そのものを知らなかった」「手続き方法がわからなかった」「誰にも聞けなかった」と話します。案内がすべて日本語。申請が必要とも書いていない。そうした“情報の壁”が、子どもたちを学校から遠ざけているのです。
In many non-enrollment cases, parents say they “didn’t even know there was a system,” or “didn’t know how to apply,” or “had no one to ask.” Information is only in Japanese. Some notices don’t even say that applications are required. These “information barriers” are keeping children out of school.
学校現場にも余裕がない
もちろん、学校側も「来た子は受け入れたい」という姿勢はあります。しかし、日本語が通じない、保護者と連絡が取れない、文化や宗教への配慮が難しい――そんな不安を、現場の教員がひとりで抱えてしまっているケースが多くあります。通訳も教材もないまま、担任が試行錯誤で対応している学校も少なくありません。
Of course, schools want to welcome every child who comes. But they face many difficulties—language barriers, lack of communication with parents, and cultural or religious considerations. Teachers are often left to handle these challenges alone, with no interpreter or materials, relying only on trial and error.
「学ぶ機会」だけでなく、「つながる機会」が必要
小学校は、外国人家庭にとって日本社会との“最初の接点”です。ここで安心できなければ、「この街では暮らせない」と感じてしまうこともあります。逆に、丁寧な案内や温かい対応があれば、「ここで子育てしていける」と感じてもらえるはずです。学ぶ以前に、「つながる」ための場づくりが求められています。
Elementary school is the first point of contact between foreign families and Japanese society. If it’s a cold, confusing experience, they may feel they can’t live here. But with clear communication and warmth, they may feel this is a place where they can raise their children. Before learning can begin, we must create space for connection.
“橋渡し”という支援が、未来をひらく
通訳、多言語での案内、入学前の相談会、保護者同士のネットワークづくり――これらは決して大がかりな制度ではありません。でも、たった一人の子どもが迷わず学校に通えるようになる。その力を、私たちは見過ごすべきではありません。
Interpreters, multilingual materials, pre-enrollment orientations, and parent support networks—these aren’t large-scale systems. But they can make a huge difference. Just one child being able to attend school with confidence—that’s powerful. And we must not overlook that power.
“共に生きる社会”の入り口に立って
「外国人の小学校受け入れ」は、教育の話であると同時に、社会の在り方の話でもあります。制度を整えるだけでは不十分です。一人ひとりの不安に耳を傾け、最初の一歩をともに支える姿勢――それこそが、“共に生きる社会”の本当のスタートラインなのかもしれません。
“Foreign children entering elementary school” isn’t just about education—it’s about how we build our society. Creating systems isn’t enough. Listening to each individual’s concerns, supporting that first step—that may be where a truly inclusive society begins.
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。