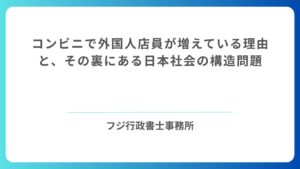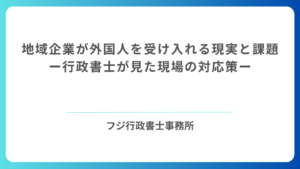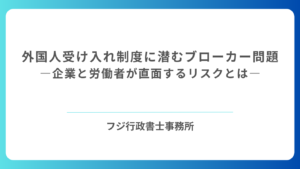近くの国へ働きに行くのが当たり前に
外国人労働者の国際移動は、遠い国よりも「近い国」への移動が主流です。その理由は明快で、距離が近ければ移動費が安く、言語や文化も似ているため、適応しやすいからです。
たとえば、ベトナムやフィリピンの労働者は、日本や韓国、台湾などへ多く渡航しています。ヨーロッパでは、ポーランドやルーマニアといった東欧の労働者がドイツやイギリスなどの西欧諸国へ。アメリカには、中南米から多くの移民労働者が集まります。
これらの地域では、長年にわたり労働者を受け入れてきた歴史があり、制度も整っています。既に身内や知人が働いているケースも多く、新たに移動する人にとって安心材料になっています。雇用ネットワークが形成されている国ほど、外国人労働者にとって選ばれやすい場所になっているのです。
遠くの国は魅力的でも、リスクが大きい
一方、遠方の国へ行くには高いハードルがあります。まず、言語や文化の違いは日常生活や仕事で大きな壁となります。さらに、ビザの取得が難しかったり、移動費や生活費が高額になる場合も多く、手元に残るお金が少なくなりがちです。
たとえば欧米諸国では賃金は高いものの、家賃や食費、交通費などの生活コストも非常に高いため、結果的に十分な送金ができないというケースが見られます。これは、母国への送金を目的とする労働者にとって大きな問題です。
その点、近隣国であれば生活コストが比較的安く、移動費も抑えられるため、出費に対するリターンが大きくなります。たとえ賃金が欧米ほど高くなくても、実質的な「得」を感じやすく、結果的に近くの国が選ばれる傾向にあります。
また、近隣国間では経済圏が形成されていることも多く、制度上も人材の移動がスムーズです。ヨーロッパのEU域内移動、ASEAN諸国間の自由化などがその例で、こうした政策も近距離志向を後押ししています。
労働力不足と外国人受け入れの現実
少子高齢化が進む先進国では、外国人労働者の受け入れはもはや避けられない課題です。日本やドイツ、カナダなどでは労働力不足が深刻で、外国人労働者に頼らざるを得ない状況が広がっています。
とくに介護、建設、製造、農業などの現場では人手が確保できず、外国人がいなければ現場が回らないという声も多く聞かれます。今後さらに人口が減れば、この傾向は一層強まり、外国人受け入れの必要性は高まっていくでしょう。
一方、送り出す側の国にとっても、出稼ぎ労働者の送金は大きな外貨収入源です。フィリピンやバングラデシュなどでは、海外送金がGDPの数%を占めるほど重要な存在になっています。つまり、外国人労働者は送り出す国・受け入れる国、双方にとって経済的に欠かせない存在となっているのです。
今後は、単なる労働力確保にとどまらず、外国人が働きやすく、定着しやすい環境をどう整えるかが問われていきます。労働者の人権を守り、送り出し国との信頼関係を築くことが、持続可能な受け入れの鍵となるでしょう。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。