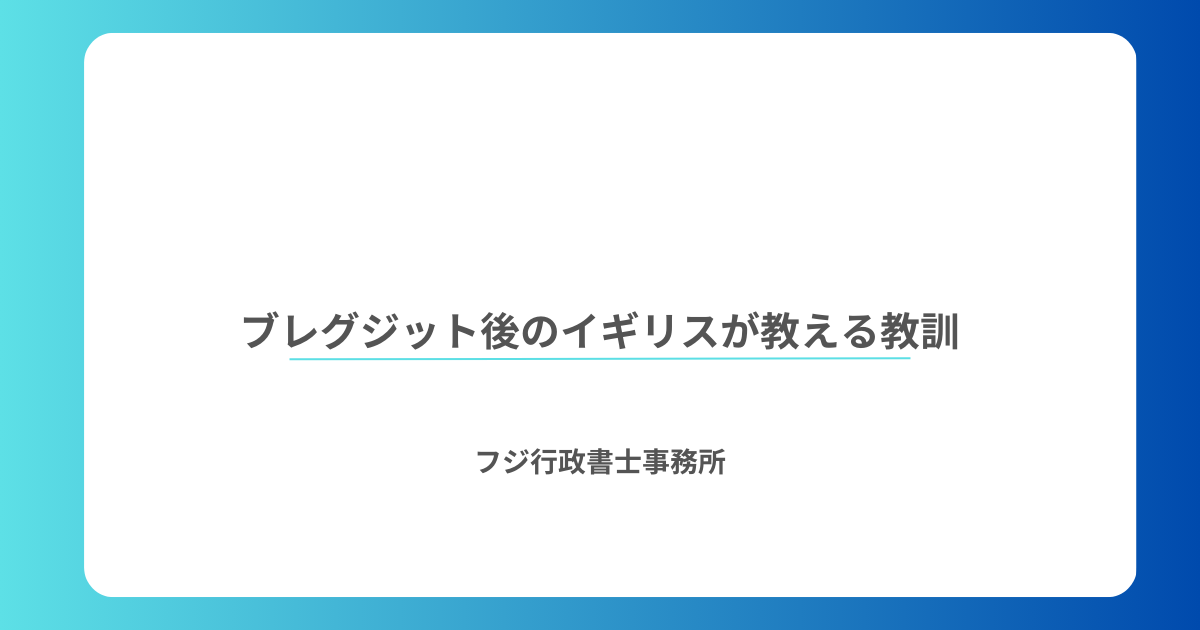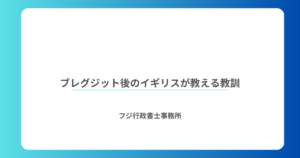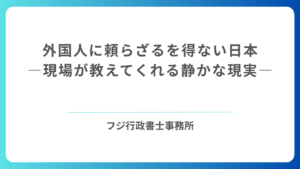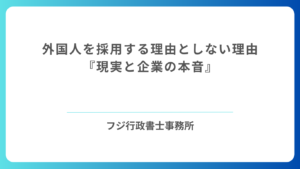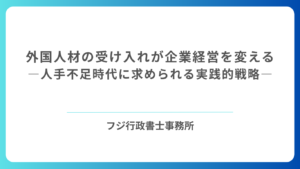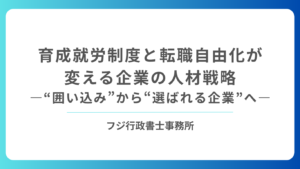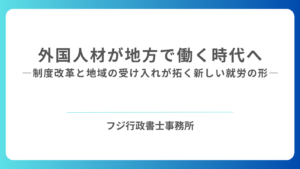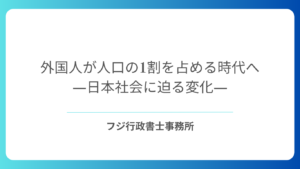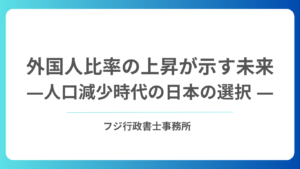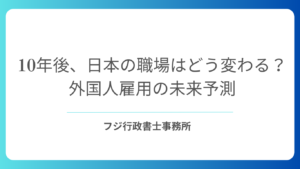ブレグジットがもたらした現実と労働力不足の深刻化
イギリスがEUを離脱した、いわゆる「ブレグジット」は、同国の経済や社会にさまざまな影響を及ぼしました。とりわけ深刻なのが、外国人労働者の急激な減少によって引き起こされた労働力不足の問題です。ブレグジット以前のイギリスでは、EU加盟国から多くの外国人が流入し、農業、建設業、物流、介護、飲食業などの現場を支えていました。彼らの存在は、いわば社会インフラの一部として欠かせないものであり、日々の生活や産業活動の基盤を担っていたのです。
ところが、EU離脱後には、こうした外国人労働者の多くが帰国を余儀なくされたり、新たな入国が制限されたことによって、現場での人手が一気に足りなくなりました。農作物の収穫が遅れ、建築現場では工期の遅延が続出し、飲食業界ではスタッフ不足で営業時間を短縮する店も相次ぎました。さらに、物流の停滞によりスーパーや飲食店の棚が空になるなど、消費者の日常生活にも影響が出始めたのです。
企業は人手不足により業務の継続が困難となり、生産性が落ちる一方で、サービスの質の低下やコストの上昇が避けられなくなりました。こうした現象が連鎖的に起こることで、イギリスの経済全体が低迷し、物価の高騰というかたちで市民生活を圧迫するという悪循環が生じています。
「移民縮小」に潜む社会分断とその弊害
ブレグジットを推進する背景には、「移民が多すぎる」という国民の強い不満がありました。一部の人々は、外国人が増えすぎたことによって治安が悪化した、文化的な軋轢が生じた、自国民の仕事が奪われた、という懸念を抱いており、それが政治的な圧力となって外国人の受け入れ制限という政策につながっていったのです。
しかし、移民の制限が社会全体にもたらしたのは、労働力の減少だけではありませんでした。多様な価値観を持つ人々が共存する中で、排除や対立の感情が広がり、社会の一体感が失われる事態となりました。国家として何かを決定すべき場面で、意見がまとまらず、分裂が深まるという現象が現実となったのです。
さらに、移民政策の転換がもたらす影響は、単なる経済的な損失にとどまりません。共通の目標や価値観を持てない社会は、いざという時に力を発揮できず、国家のガバナンスそのものが揺らぎます。ブレグジット以降のイギリスは、そのような「分断」が深刻な社会問題となって表面化しており、外国人を一括りにして制限することが必ずしも国益にかなうとは限らないという現実を突きつけられています。
他国が学ぶべき教訓と今後の政策への示唆
イギリスの事例が私たちに教えてくれるのは、外国人労働者を「単なる働き手」としてではなく、社会や経済の持続可能性を支える不可欠な存在として捉える必要があるということです。彼らの存在があってこそ、多くの産業が円滑に回っており、社会の安定が保たれています。むしろ外国人労働者の減少によって、真っ先に影響を受けるのは市民の日常生活や基本的な公共サービスである、という視点を忘れてはなりません。
そして、外国人の受け入れをどうするかという問題は、一国だけの事情や感情論で決められるものではなく、国際的な経済構造や人口動態、社会の多様性といった複合的な要因を踏まえて慎重に判断する必要があります。単に「外国人を減らす」といった短絡的な政策は、長期的には自国経済を弱体化させ、ひいては国際的な信頼の低下にもつながりかねません。
他国がイギリスと同じ道をたどらないためにも、労働力の確保と社会統合のバランスをいかに取るかが問われています。外国人との共生は、避けて通れない現実です。その現実を正面から見据えたうえで、制度的・文化的な整備を進めることこそが、持続可能な社会づくりへの第一歩であると言えるでしょう。イギリスの経験を「他人事」ではなく「自分事」としてとらえ、失敗から学ぶ姿勢が今後の国づくりに欠かせません。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。