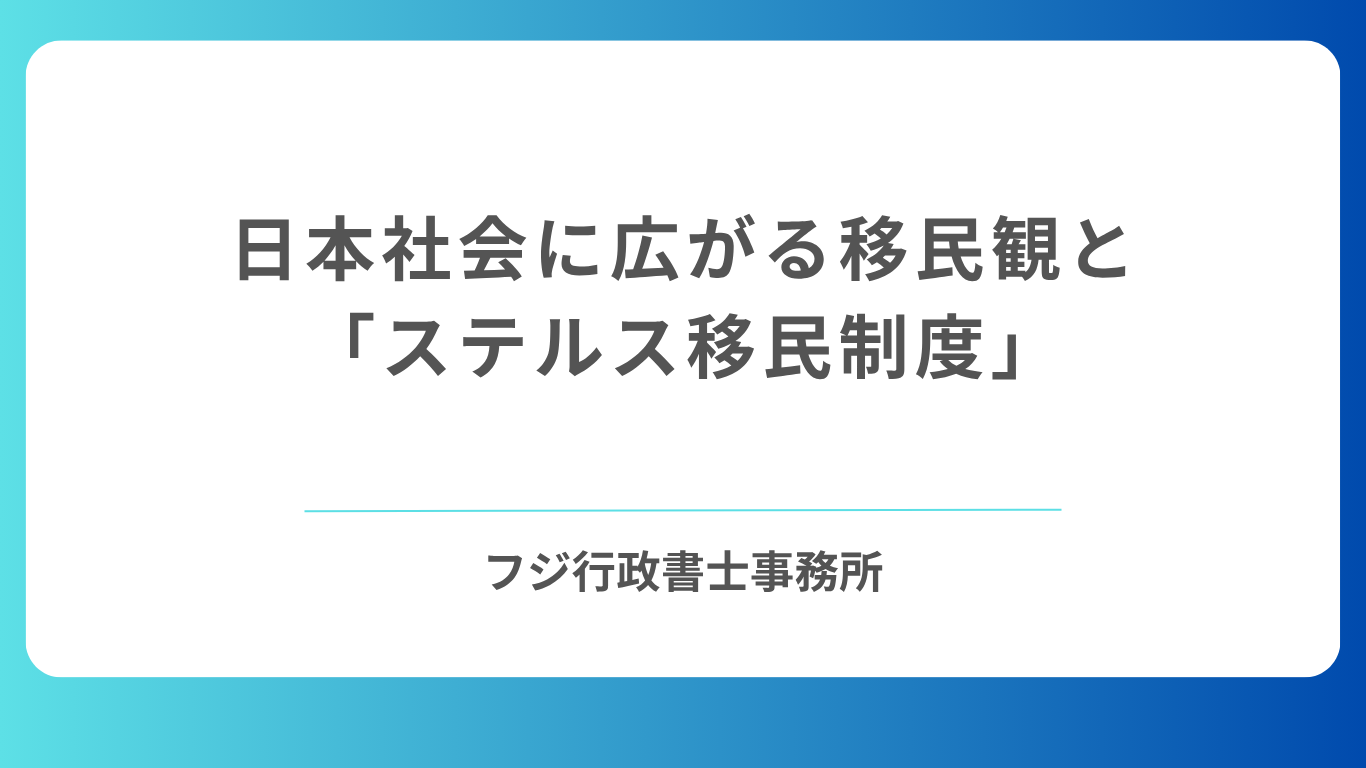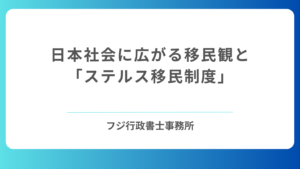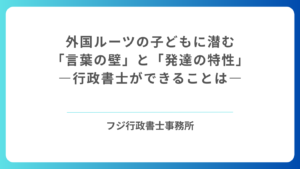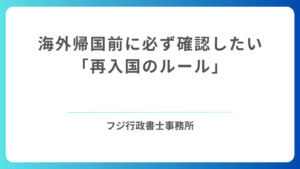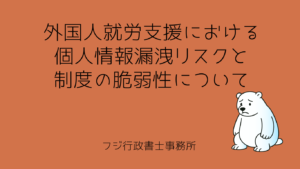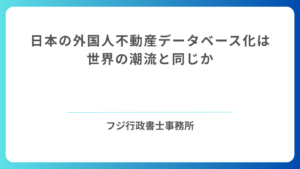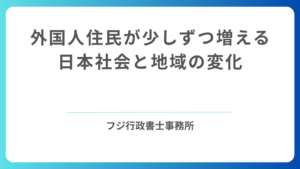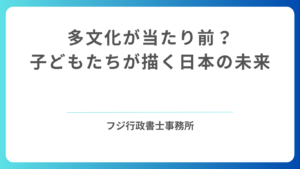海外が注目する日本社会の「移民観」と現状
ここ数年、海外の報道では、日本社会における外国人や移民への見方に注目が集まっています。日本では、移民を「低賃金で働く人」「日本語が通じにくい存在」「学校を途中でやめる子どもが多い」「治安の悪化を招く」など、いくつかの固定的なイメージと結びつけてとらえる傾向があるとされています。実際には、こうした印象はデータや現場の実態と必ずしも一致しているわけではなく、SNSや報道によって一方的に強調され、社会に広がっていく構造があると指摘されています。
また、日本の外国人受け入れ制度は、国際的には「ステルス移民制度」と呼ばれることがあります。これは、移民政策を明示的に掲げていない一方で、技能実習や特定技能といった制度を通じて多くの外国人労働者を受け入れているという仕組みです。しかし、生活支援や言語教育などが十分に整っておらず、外国人が地域で孤立したり、住民の側に誤解や不安が生まれやすい土壌となっているとされています。
制度と実務のギャップが生む課題
入管実務に携わる中で感じるのは、制度の理念と現場での運用に少なからず隔たりがあるということです。例えば、特定技能や技能実習では一定の日本語力が求められているものの、実際には職場や地域社会で十分なサポートを受けられず、生活面で孤立してしまうケースがあります。企業側も受け入れ態勢が十分に整っていないまま採用を進めていることがあり、結果として、言語や文化の違いが偏見の引き金になってしまう場合があります。
一方、地域住民の側も制度の背景や仕組みを十分に理解していないことが多く、外国人の数が増えたこと自体に不安を感じたり、治安や生活習慣への懸念を抱くことがあります。制度面での説明不足や、生活支援の欠如が、双方のすれ違いを深める要因となっています。
地域で見える現場の変化
大阪府箕面市では、留学生や技能実習生、特定技能の労働者が以前よりも身近な存在になってきました。学校行事や地域のイベントに外国人家庭が参加する機会も増えていますが、言語の壁や行政情報の伝達不足により、各種制度を十分に活用できていない事例も少なくありません。
たとえば、扶養控除や児童手当の申請、在留資格変更の手続きなどは、情報が届かなければ期限を逃したり、誤って処理してしまうリスクがあります。こうした制度と生活の間に生じる溝を埋めるには、行政機関や支援団体だけでなく、実務を担う専門家の役割も欠かせません。現場に立つ立場だからこそ見えてくる課題が数多くあります。
今後に向けた視点と提案
海外の報道が示す「偏見」や「ステルス移民制度」という言葉は、外部からの批判というよりも、日本社会が抱える制度設計と地域運用の課題を映し出したものといえます。今後は、受け入れ政策をより明確に打ち出すとともに、言語・生活支援を含めた実効的な統合政策を整えることが求められます。
実務の現場では、在留資格の手続きを単に代行するだけでなく、制度の背景や利用できる支援策を丁寧に伝えること、地域社会との橋渡し役を担うことが重要になります。偏見や誤解を少しずつ減らし、地域と外国人が共に生活していくための基盤を整えることこそが、今後の大きな課題といえるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。