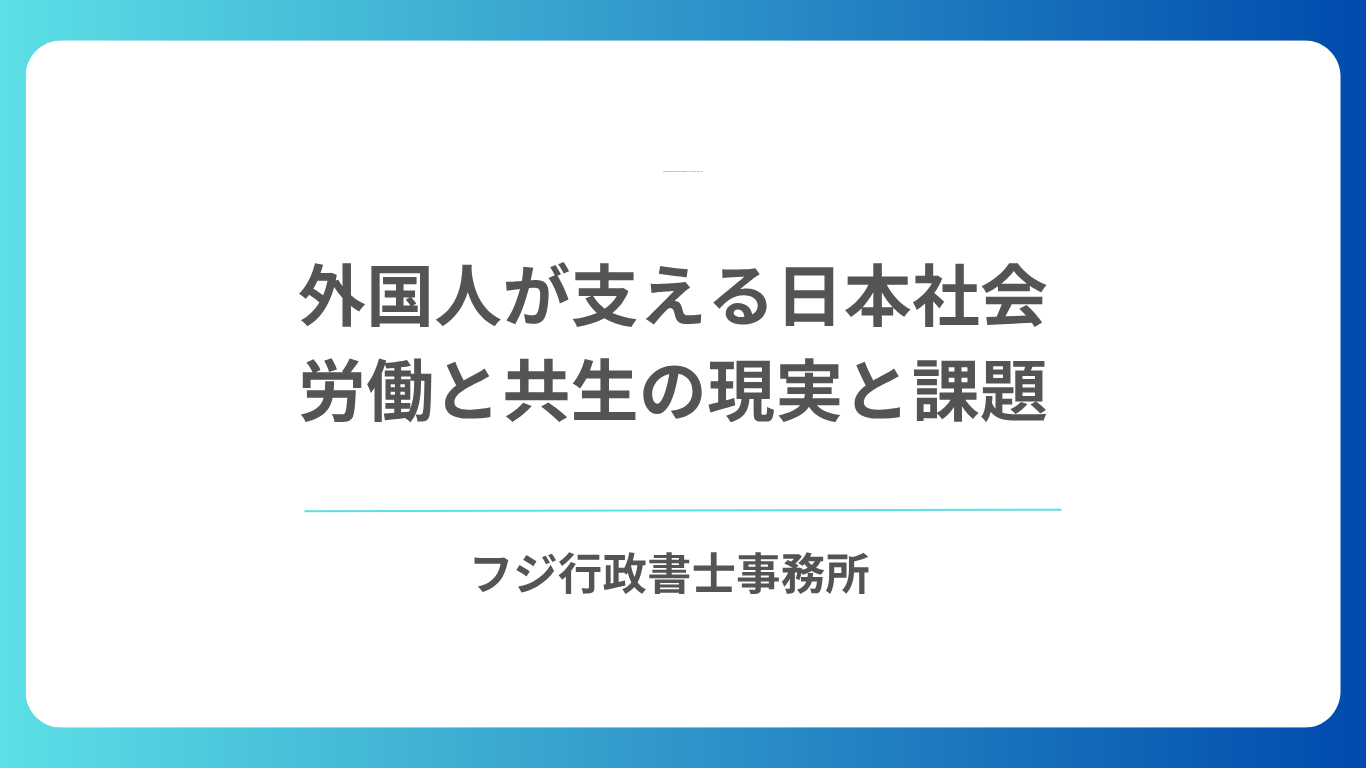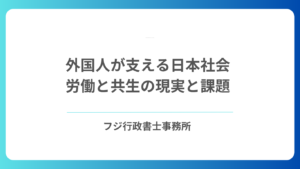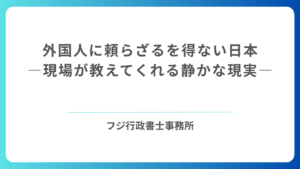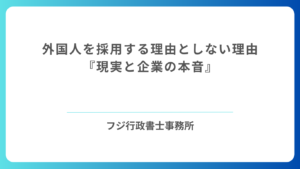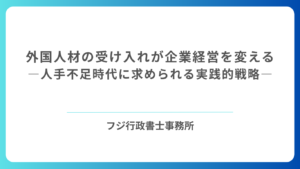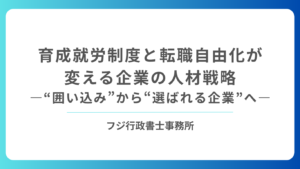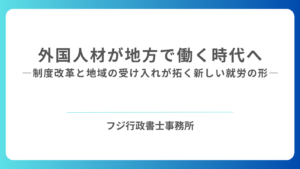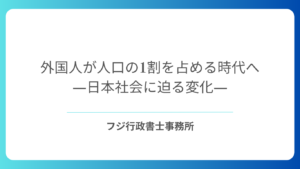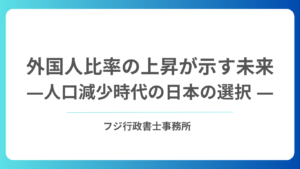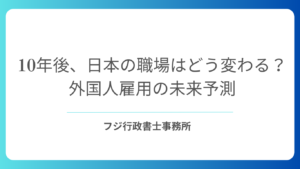外国人が支える労働力の実態
日本社会において、外国人の存在感がこれまでになく増しています。2025年1月時点の統計によると、国内に居住する外国人の数は約367万人に達し、前年より35万人増加しました。この増加は3年連続で過去最多を更新しており、外国人が日本の労働市場を支える柱となってきていることがうかがえます。特に都市部ではその傾向が顕著で、若年層の中でも20代の約1割以上が外国人であるという地域も見られます。
厚生労働関連のデータからは、外国人労働者の受け入れが急速に進んでいることもわかります。特に人手不足が深刻な業種、たとえば介護や建設、外食や農業といった分野では、外国人の力がなければ業務が成り立たないという声も聞かれます。労働力としての外国人は、補完的な役割を超え、すでに不可欠な存在となっているのです。
増加に伴う社会の緊張と対話の必要性
外国人の増加は経済面で一定の効果をもたらしている一方で、生活や文化の違いに起因する摩擦や地域住民とのすれ違いも生じています。実際、ゴミ出しのルールがわからない、騒音の感覚が異なる、地域の行事への参加意識が低いなど、生活習慣の違いからトラブルが起こることもあります。また、行政手続きの複雑さや言語の壁によって、支援制度の利用が進まないケースもあります。
こうした状況に対応するため、行政機関は外国人対応を一元化する体制づくりを進めています。住民からの相談を受け付ける窓口を設けたり、通訳の配置や多言語での案内を充実させたりと、環境整備が進められています。ただし、まだ十分とは言えず、自治体ごとに温度差があるのも事実です。地域社会が外国人とどのように向き合っていくか、共生に向けた対話の場づくりが求められています。
労働力ではなく「生活者」としての視点へ
日本に住む外国人を、単なる労働力ではなく「生活者」として受け入れる視点が重要になっています。外国人の中には、長期的に日本での生活を希望する人や、すでに家族と共に生活している人も多くいます。そうした人々に対しては、仕事だけでなく、教育・医療・子育て・住宅といったあらゆる面での支援が必要となります。
たとえば、日本語教育の機会を広げることや、子どもたちの学校での適応支援、外国人保護者とのコミュニケーション支援、多文化共生センターの設置などが挙げられます。しかしながら、こうした取り組みは一部の地域に限られており、全国的な整備には課題が残ります。「共に暮らす」ためには、日本人と外国人が互いに理解を深め、文化や価値観の違いを尊重し合う姿勢が欠かせません。
外国人政策の再設計が問われている
これまでの外国人受け入れは、労働力不足への一時的な対応として進められてきた側面があります。しかし今後、少子高齢化によって労働人口の減少が続く中で、外国人の受け入れは国家の中長期的な人材戦略の一環として捉える必要があります。教育やキャリア形成の支援、在留の安定化、社会参加の促進といった観点から、受け入れ方を再設計することが求められます。
他国では、移民の社会統合を前提とした制度整備が進んでおり、日本でもそのような枠組みを参考にする動きが始まっています。具体的には、外国人に対する日本語教育の義務化、就労後のキャリア支援、家族帯同の条件緩和などが検討されています。外国人を「一時的な人手」ではなく「共に社会を築く仲間」として受け入れていくには、行政・企業・地域社会が一体となって制度と意識の両面からの変革を進める必要があります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。