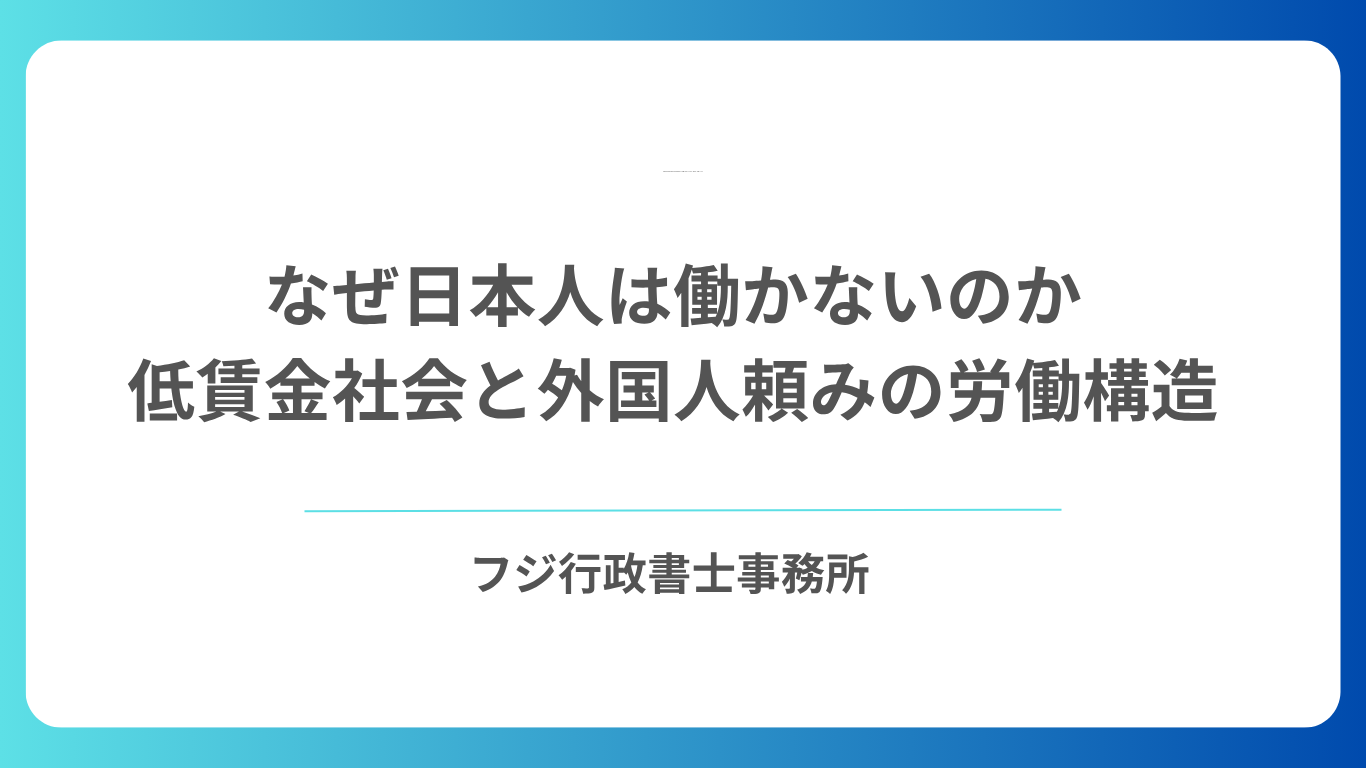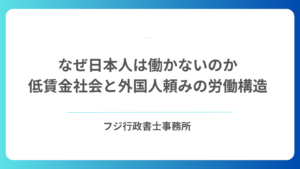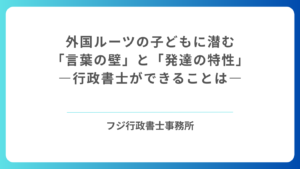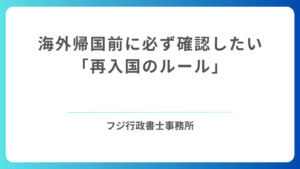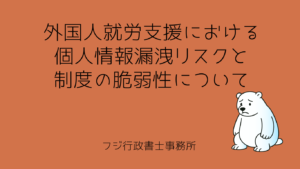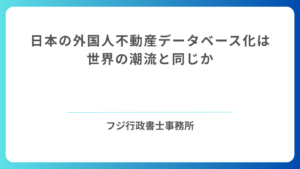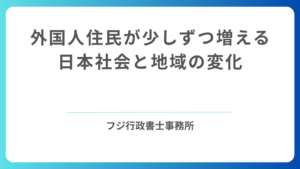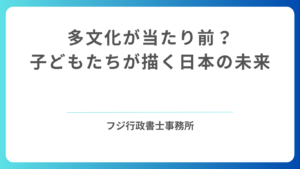「移民政策ではない」と言いながら
日本政府はこれまで一貫して、「日本は移民国家ではない」と表明してきました。総理大臣や法務大臣の発言においても、「労働力として外国人を受け入れるが、それは移民政策ではない」「あくまで一時的な滞在」といった説明が繰り返されています。これは、日本社会が長らく「単一民族・単一文化」という自己認識を持ち、それを前提に社会制度を設計してきた歴史と関係しています。
一方で、現実にはすでに多くの外国人が日常的に日本で働き、暮らし、地域社会の一員として生活しています。技能実習制度、特定技能、留学生のアルバイト、さらには永住権を取得した外国人家族まで含めれば、すでに相当数の「移民的存在」が日本に根づいているのです。
つまり、表向きは「移民ではない」と否定しながら、実態としてはすでに移民に依存している。このねじれた構図こそが、今の日本社会の矛盾を象徴しています。
現場は“移民”として扱っている
「この仕事は外国人がいなければ回らない」――そう言われる業種は少なくありません。介護、外食、建設、農業、製造など、多くの現場では日本人が集まらず、外国人なしでは成り立たない状況が続いています。
技能実習制度は、建前として「人材育成の国際貢献」を掲げていますが、実際には単純労働の担い手として活用されているケースがほとんどです。特定技能制度も、形式上は“在留資格の一種”に過ぎませんが、就労と生活の定着を前提とした制度設計であり、実質的には移民政策の一部といえる内容になっています。
現場の企業や地域住民にとっても、もはや外国人労働者は「一時的な存在」ではありません。彼らは数年にわたって働き、家族を持ち、学校に通い、地域イベントにも参加します。つまり、実態は「住民」であり、「生活者」であり、「移民」なのです。
それでも、制度上は「一時的な在留者」であるという建前が維持され続け、受け入れ側も送り出し側も、その枠内で動くしかない。この“実態と制度の乖離”が、トラブルや不信感、制度疲労の原因になっているのです。
なぜ「移民」と呼ばれたくないのか
ではなぜ、日本はここまで「移民」という言葉を避け続けるのでしょうか。背景には、戦後の社会的価値観や、外国人に対する根強い不安感、治安・教育・福祉コストに対する懸念などが複雑に絡んでいます。
特に地方では、「外国人が増えると治安が悪くなるのではないか」「日本の文化が壊れるのでは」といった漠然とした不安が根強く、政治家にとっても「移民政策を推進している」と見られることはリスクになります。そのため、明確に「移民政策をやります」と言うのではなく、「必要な人材を限定的に受け入れる」という形を取り続けるのです。
しかしこのような曖昧な姿勢こそが、現場を混乱させ、政策の持続性を損なっている原因にもなっています。外国人にとっても、自分の立場が不安定で、制度がころころ変わる国に将来を託すのは不安です。
移民ではない、という言い方は、日本人のための“安心材料”かもしれませんが、実際に生活する外国人にとっては不安材料にしかならない。この構造が放置されれば、外国人の定着率は下がり、人材は他国に流れていくでしょう。
「移民」とどう向き合うかが問われている
今の日本に必要なのは、「移民」という言葉を避けることではなく、「移民的な実態」を正しく認識し、その上で制度や社会の受け入れ体制を整えることです。
定住者・永住者・日本人と結婚した外国人、さらには特定技能や留学生として来日し、やがて地域に根づく人々を、「生活者」としてどう支えるか。教育、医療、税制、年金、子育て、住宅、差別防止……あらゆる面で、共に生きる仕組みを構築する必要があります。
そして、そのためにはまず国民全体が「もう日本は移民社会に入っている」という事実を受け止めることが出発点です。理想論としての“移民反対”ではなく、現実社会としての“移民との共生”が問われているのです。
外国人がいなければ社会が回らない。けれども、外国人は永住させたくない。――この矛盾を抱えたままでは、制度も社会も行き詰まります。日本は「移民ではない」という建前をいつまで続けられるのか。そして、その建前の先にどんな未来を描くのか。今こそ、覚悟が問われています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。