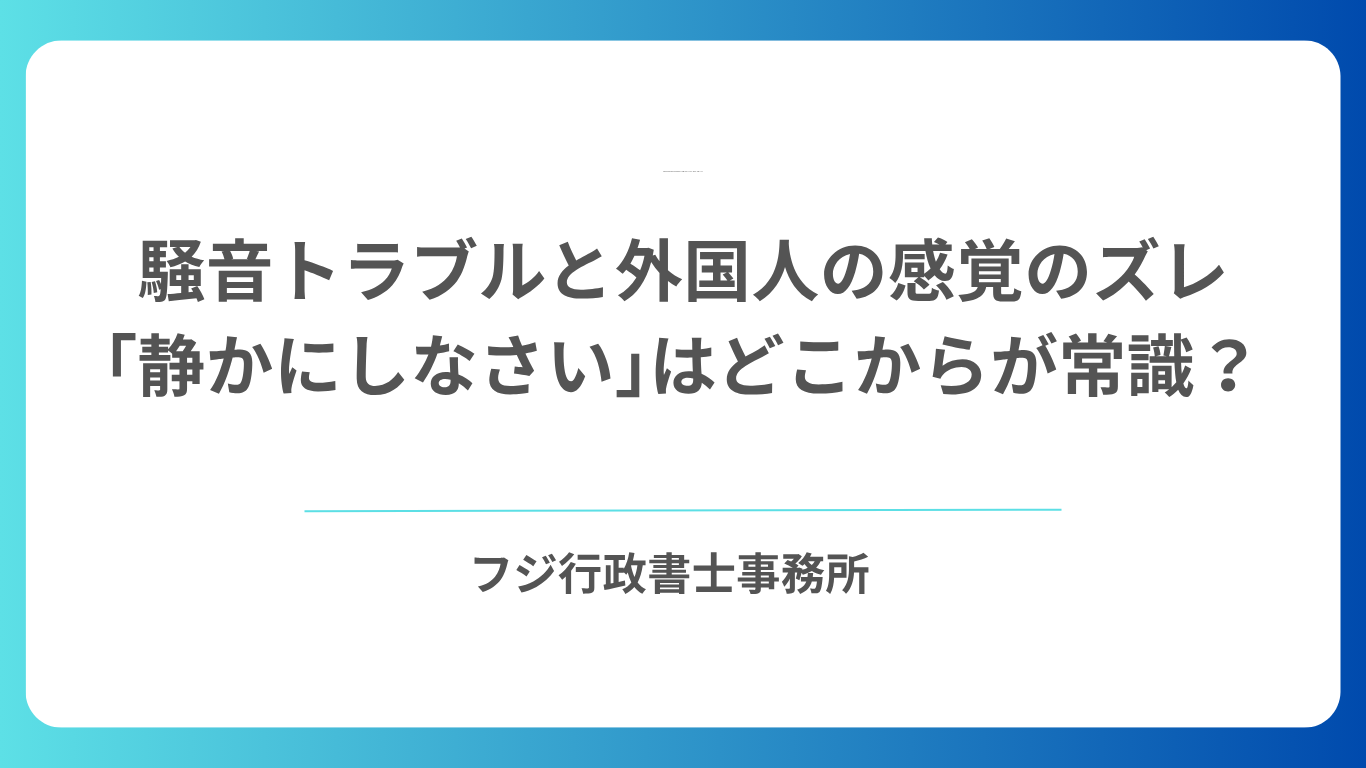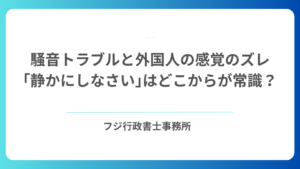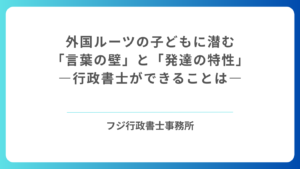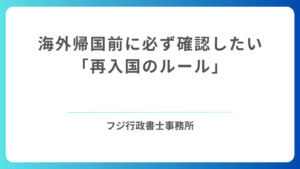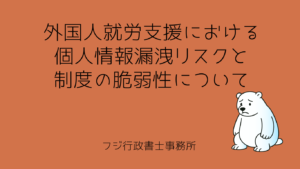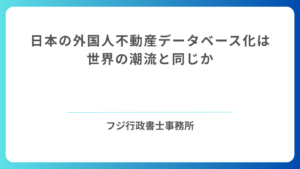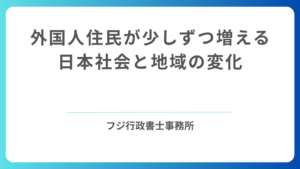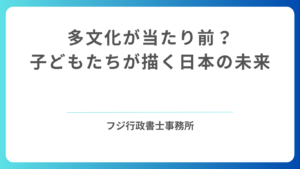日本では「静かすぎる」のが常識?
日本で暮らす外国人からよく聞かれる疑問のひとつに、「どうしてこんなに音に敏感なのか」というものがあります。特に集合住宅では、ほんの少しの生活音や話し声に対して「うるさい」と感じる住人が多く、外国人にとっては戸惑いの種になっています。ある留学生は、「昼間にテレビを少し大きめにつけていただけで、管理会社から注意を受けた」と話していました。彼にとっては、家の中で音楽やテレビを楽しむのは当たり前のことで、何も問題があるとは思っていなかったのです。確かに日本では、「騒音=迷惑」という認識が強く、とりわけ静けさを重んじる文化があります。夜はもちろん、日中でも生活音には配慮するのが当たり前という感覚が、多くの日本人に根づいています。しかし、この“常識”は、海外から来た人にとっては必ずしも共有されているわけではありません。
音の感じ方は国によってこんなに違う
音に対する感覚は、文化や生活環境によって大きく異なります。例えば、ベトナムやフィリピンでは、大家族で暮らし、家の中でもにぎやかに会話したり音楽を流したりするのが日常です。道ばたでも人の声やバイクの音が絶えず、日本のように「静かにしなさい」としつけられることはあまりありません。また、中東出身の方からは、「昼間に子どもが走り回る音にまで苦情が来るとは思わなかった」と驚きの声がありました。彼の国では、子どもが元気に遊ぶ音は自然なことで、迷惑とされることはほとんどないそうです。このように、“音”に対する感覚は決して世界共通ではありません。むしろ、日本のほうが“特別に静か”な社会であるとも言えます。そして、その静けさを破ることが、「マナー違反」や「トラブルのもと」となりやすい現実があります。
トラブルになる前に伝えておくことの大切さ
外国人がこうした文化の違いを知らないまま生活を始めると、思わぬ形でトラブルに発展してしまうことがあります。「足音がうるさい」「洗濯機の音が夜まで響く」「電話の声が深夜まで聞こえる」など、本人に悪気がなくても、周囲の住民にとっては大きなストレスとなるのです。行政書士として在留に関する相談を受ける際、「近所トラブルで警察を呼ばれてしまった」「管理会社から退去を勧められた」といった声を聞くこともあります。こうした場合、外国人の方は何が問題なのか理解できず、理不尽に感じてしまうこともあります。そこで重要なのが、「音に対する日本の感覚」を早い段階で伝えておくことです。契約時の説明に一言添える、不動産会社と連携して注意事項を翻訳して渡す、入居後のオリエンテーションで事例を紹介するなど、小さな工夫がトラブル予防につながります。また、本人に直接注意するよりも、第三者である行政書士や支援団体がやんわり伝えることで、受け入れやすくなるケースもあります。
音を“迷惑”ではなく“違い”として受け止めるために
もちろん、すべてを外国人側の責任とするのは適切ではありません。日本人の側にも、「違い」を理解する柔軟さが求められます。「非常識」「ルール違反」と決めつけるのではなく、「どうしてそうなったのか」という背景を知ることで、感情的な対立を防ぐことができます。地域によっては、多文化共生に向けたマンション管理のガイドラインを整備したり、掲示物に多言語対応を取り入れたりして、外国人居住者との共生を進めている例もあります。そうした取り組みが広がれば、“音”にまつわるトラブルも減っていくかもしれません。音の問題は、とても小さなことのようでいて、実は人間関係や在留生活の安定に深く関わっています。行政書士としても、制度や書類の枠を超えた“暮らしの支援”を意識していくことが求められています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。