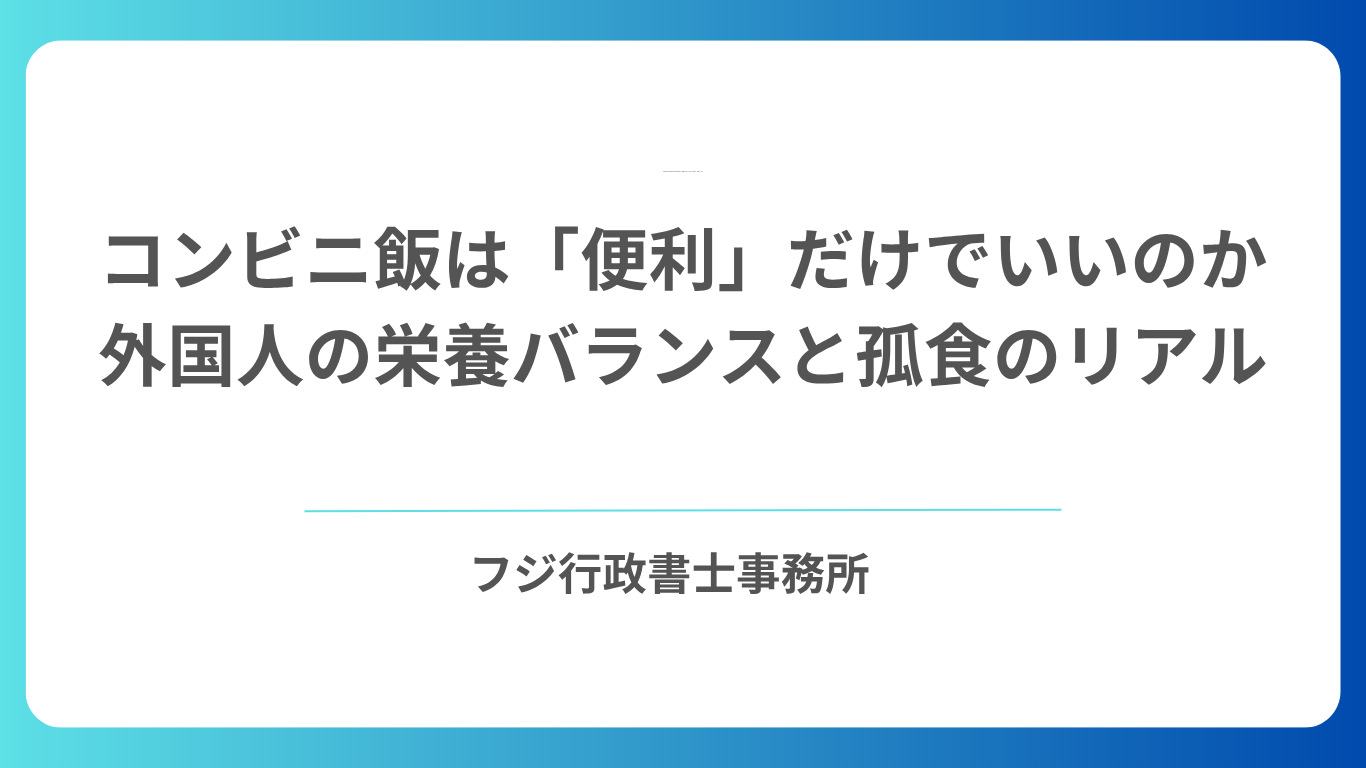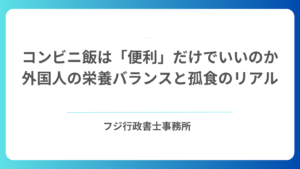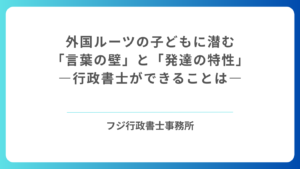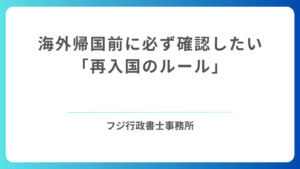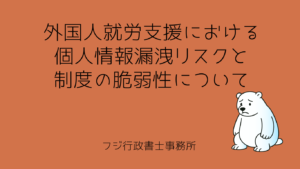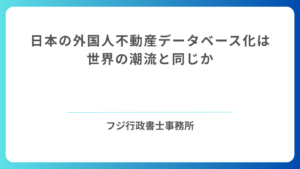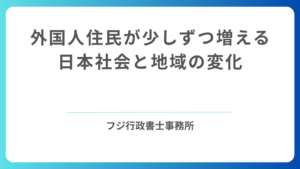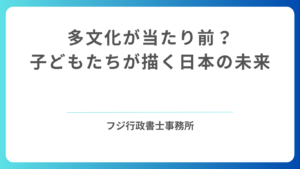コンビニは外国人の味方か、それとも栄養の落とし穴か
日本で暮らす外国人にとって、コンビニは非常に頼れる存在です。24時間営業、メニューの豊富さ、手頃な価格、清潔な店舗――初めて日本に来た方にとっては、まさに救世主のような場所です。とくに、技能実習生や留学生など、限られた時間と予算で生活する人にとっては、料理をせずに済む便利さが何より魅力です。実際、行政書士として在留手続きや生活相談を受けていると、「ほとんど毎日コンビニで食事を買っています」という声を多く聞きます。弁当、おにぎり、カップ麺、冷凍食品。味も安定しており、失敗が少ないという安心感もあります。しかし、こうした便利さの裏で、気づかぬうちに栄養バランスを崩しているケースが少なくありません。特に、単身で来日している若い外国人は、野菜不足やタンパク質の偏り、糖質の過剰摂取など、長期的に見ると健康へのリスクを抱えていることが多いのです。
コンビニ依存がもたらす「孤食」と健康の不安
ある中国人技能実習生は、「仕事終わりが遅く、寮にはキッチンも狭くて調理が難しい。だからコンビニで済ませるしかない」と話していました。別のネパール人留学生は、「日本語が不安で飲食店に入りづらく、自炊も苦手。だから毎日おにぎりとカップ麺で過ごしている」と語ってくれました。彼らはコンビニの便利さに助けられている反面、自分の食生活が偏っていることを自覚しながらも、改善の余地が見いだせない状況にいます。特に問題となるのが、“誰かと食卓を囲む”機会が極端に少ない点です。仲間や家族と食事を共にすることが少ないため、孤食が慢性化し、心身ともに疲弊していくこともあります。日本の職場文化も、こうした状況に拍車をかけています。実習先やアルバイト先で、忙しさから昼食をとる時間が取れなかったり、支給される食事が簡易なものであったりすることもあり、総じて「食」が軽視されがちです。体調を崩してから初めて、ようやく「食事を見直したい」と相談に来るケースもあります。行政書士として話を聞く中で、制度や法律以前に、こうした生活面のケアの必要性を強く感じることが少なくありません。
文化的背景をふまえた支援のあり方とは
日本人にとってもコンビニは便利な存在ですが、あくまで“補助的”な位置づけで利用する人が多いのに対し、外国人にとっては「生活の柱」になっていることがあります。そこに文化的・構造的な違いがある以上、単に「バランスよく食べましょう」と伝えるだけでは意味がありません。たとえば、ベトナムやミャンマーでは、家庭で毎日温かい食事を作る文化が根づいています。そのような人たちが、日本で一人暮らしとなり、料理の設備も限られ、誰かと食事を囲むこともなくなると、大きな精神的ギャップが生まれます。そうした背景を踏まえたうえで、私たち行政書士や支援者ができることは、法的な相談を受けるだけでなく、「この地域に外国人も入りやすい食堂がある」「弁当が安くて野菜も取れるスーパーがある」といった、日常に即した情報を伝えることです。また、自治体やNPOが行っている食支援や地域交流のイベントを案内するだけでも、孤立を防ぐきっかけになる場合があります。コンビニ飯は確かに便利です。しかし、「便利さ」だけに依存した生活には、見えない落とし穴があります。書類上は在留資格が安定していても、生活の土台が不安定であれば、いずれ心身に影響が出てきます。「食べること」は生きることと直結しています。外国人の相談を受ける私たちにとって、栄養や孤食という問題は、実は見過ごせない重要なテーマだといえます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。