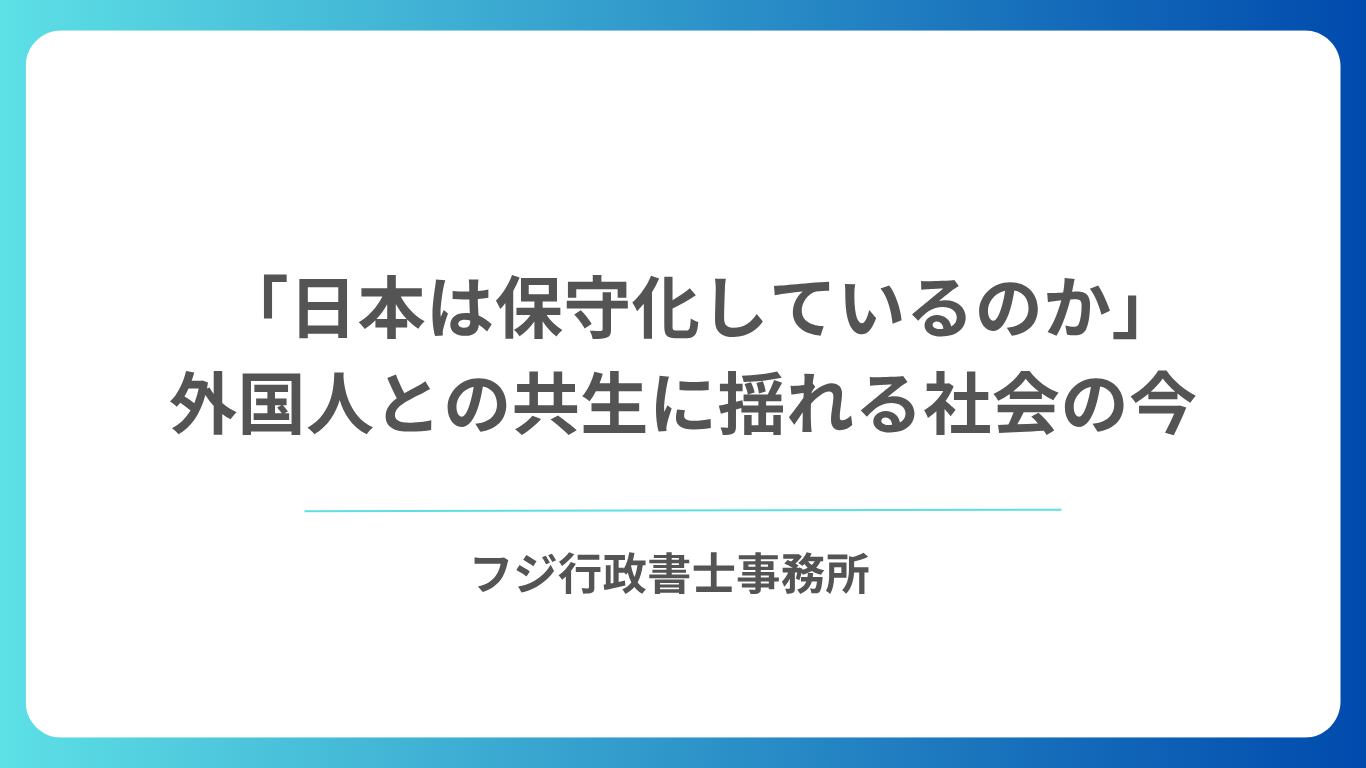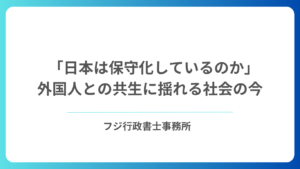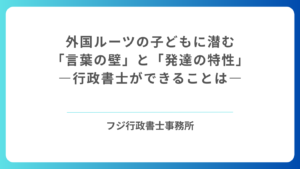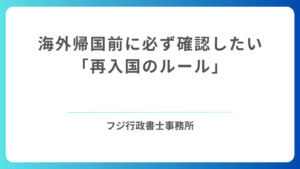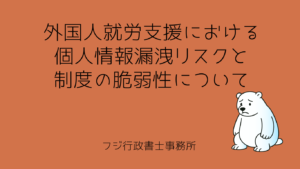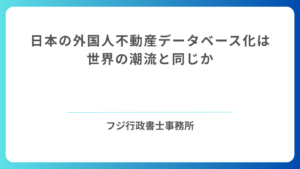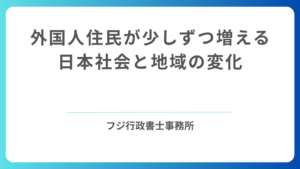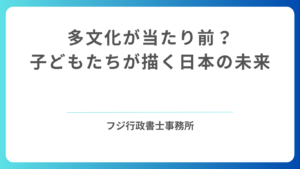広がる「変化への拒否感」──保守化の空気を感じるとき
「外国人は優遇されすぎている」「LGBT法案はおかしい」「国を取り戻すべきだ」──ここ数年、SNSや街頭、政治の場で、こうした言葉を見聞きする機会が増えました。特に選挙が近づくと、それらの言葉はさらに先鋭化し、拍手や共感を集めていきます。社会全体に「変化を拒む空気」が強まっていると感じる人も多いのではないでしょうか。実際、「外国人との共生」や「多様性の尊重」に対して拒否反応を示す言説が以前よりもずっと表に出てくるようになっています。一部では「日本社会は保守化している」とも言われますが、それは単なる思想傾向の変化だけでなく、もっと複雑で根深い“社会の内圧”によるものかもしれません。
「守りたい」という感情の背景にあるもの
なぜ今、「保守的な言葉」に共感が集まるのでしょうか。その理由の一つには、生活や将来に対する不安の広がりがあります。物価は上がっても給料は増えず、子どもの数は減り、高齢化が加速し、社会保障は不安定。こうした閉塞感のなかで、人々は「自分たちの生活がこれ以上脅かされたくない」と感じるようになります。本来「保守」とは、伝統や秩序、共同体を大切にしようという立場です。しかし、近年見られる“保守的”な言説は、何かを丁寧に守ろうというよりも、「もう壊されたくない」「変わることが怖い」という強い防衛感情に基づいています。つまり、これは思想ではなく、感情の問題です。たとえば、外国人に対する支援制度がわずかであっても、「なぜ自分たちが苦しいのに外国人に?」という疑問が先に立ちます。現実にそうなっていないとしても、「そう“感じる”」ことが怒りの源になるのです。そしてその怒りは、SNSで増幅され、政治の言葉にもなり、さらに社会に広がっていきます。
「共生」に対する本音と葛藤
本当は多くの人が、「差別はよくない」「人として尊重するべきだ」と考えています。けれども、それと同時に「自分たちの生活が圧迫されるのでは」「声を上げづらくなるのでは」といった、言葉にしにくいモヤモヤを抱えています。ここに、保守的な言説が入り込む隙間があります。「自分が大切にしてきた常識が否定されている」「気を使いすぎて本音が言えない」と感じたとき、人は変化や多様性を歓迎できなくなります。それは自然な感情です。ただ、その感情を「だから外国人はいらない」「だから制度は廃止すべきだ」といった形で爆発させてしまうと、社会全体が息苦しくなり、分断を深めてしまいます。いま必要なのは、「不安を口にすること」が悪だと決めつけることではありません。不安や不満をきちんと受け止めたうえで、「でも実際の制度はこうなっている」「実際に一緒に働いている人たちはこうして支えてくれている」という事実と丁寧に重ね合わせることです。その“中間の姿勢”こそが、今もっとも求められている態度だと思います。
社会は本当に保守化しているのか?
では、今の日本社会は本当に「保守化」しているのでしょうか。たしかに、表現や価値観に対して「それは違う」「やりすぎだ」と批判する声は増えています。けれども、同時に多くの人が「共生したい」「誰も排除しない社会にしたい」とも思っています。つまり、私たちはいま、「変化に適応しようとする力」と「変化に対する拒否感」のあいだで、揺れ動いているのです。この揺らぎは、悪いことではありません。むしろその揺らぎの中で、一人ひとりが「何を大切にしたいのか」「誰と生きていきたいのか」を考え直すチャンスでもあります。社会が“守り”に入るとき、その裏には必ず“守らなければならない何か”があります。経済的安定か、文化か、家族か、暮らしの手触りか。その何かを大切にしながら、排除ではなく、共に支える道を選ぶこと──それがこれからの「保守」と「共生」のあり方なのではないでしょうか。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。