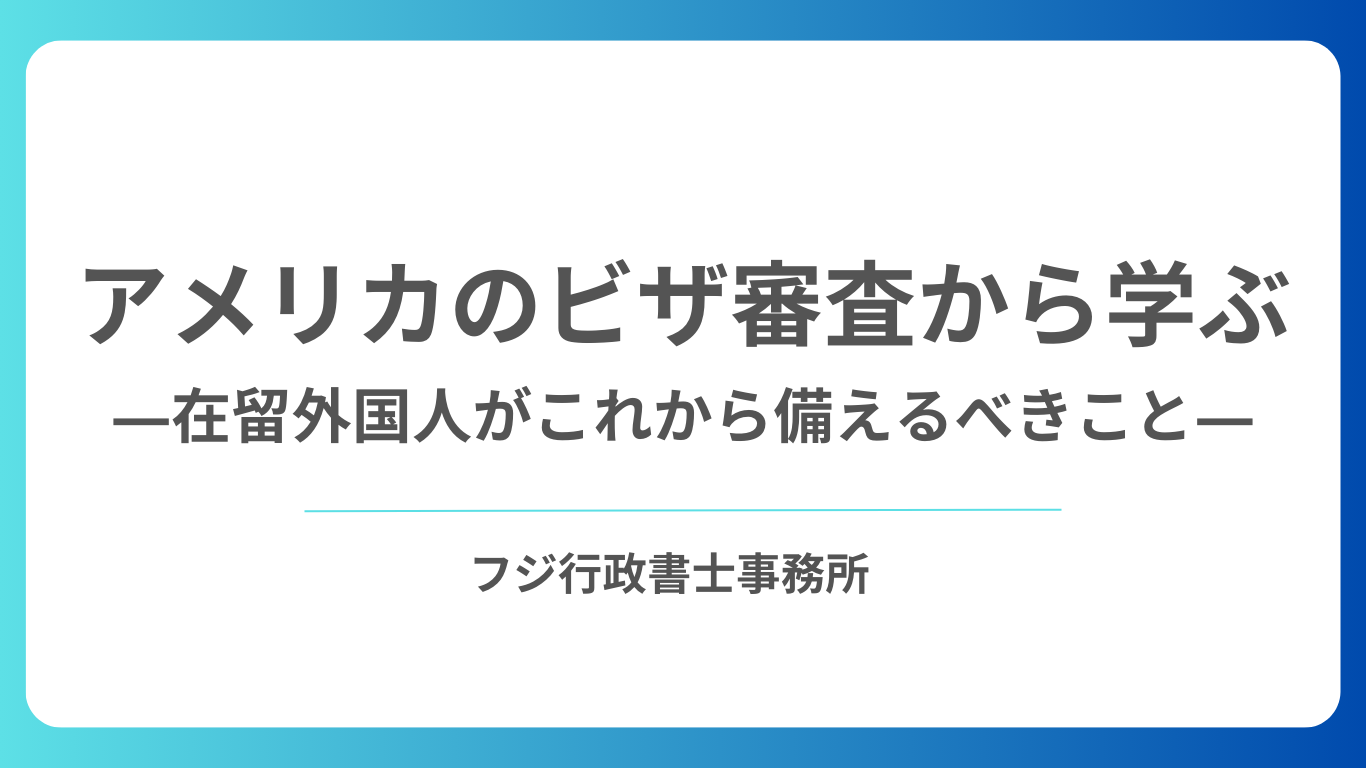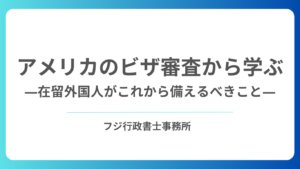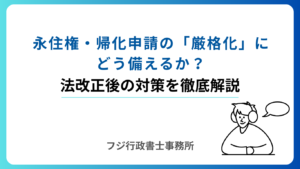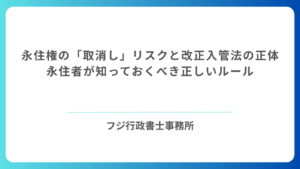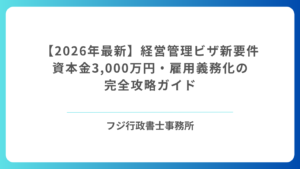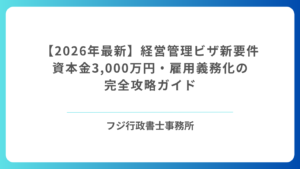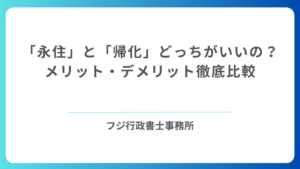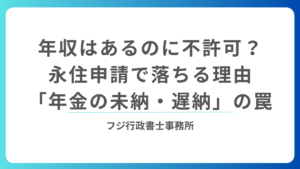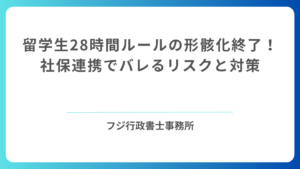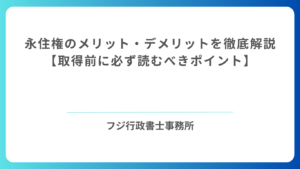アメリカ政府が発表した大規模ビザ審査とは
アメリカ政府は、有効なビザを持つ人々の記録を継続的に精査し、入国や滞在条件に違反がないか確認すると発表しました。従来は入国時や発給時の審査が中心でしたが、今後は「入国後も常に見られている」体制に変わりつつあります。
対象となるのは滞在期限の超過や犯罪行為、公共の安全に対する脅威、過激思想や組織との関わりなどです。さらに、ソーシャルメディアの利用状況も確認され、ネット上の発言や行動が直接ビザの有効性に影響することが明らかになりました。
大規模審査の背景と目的
この取り組みの背景には、治安維持とテロ防止、不法滞在問題への対応があります。これまでは入国前のチェックが中心でしたが、それだけでは不十分とされ、発給後の監視に重点が移されました。特にビザで入国した後に条件を破る人が増えると制度への信頼が揺らぐため、継続的な管理が不可欠と考えられています。
政治的な意図もあります。強い管理体制を打ち出すことは、政府の治安対策を支持層に示すアピールでもあります。また、近年はSNSを通じて過激思想や違法行為が広がるケースが多く、ソーシャルメディアのチェックは現代的なリスク対策と位置づけられています。
メリットと懸念点――良いことなのか?
この制度を肯定的に評価する人も少なくありません。危険な人物を早期に把握し排除できるため、治安維持や社会の安心感につながります。また、入国後も監視されていると意識させることで不法滞在の抑止にも役立ちます。さらに、すべてのビザ保持者を対象とすることで公平性を示し、特定の国や地域への偏見を避けられる点も利点です。
一方で、懸念も残ります。過度な監視は自由やプライバシーを制限するおそれがあります。SNSの発言が誤解され、不利益につながる可能性も否定できません。安全を守ることと自由を保障すること、その両立が大きな課題です。つまりこの制度は、治安維持には効果的でありつつ、権利保護の面で慎重さが求められる両面性を持っているのです。
日本への影響と在留外国人が備えること
アメリカの動きは日本に暮らす外国人にも示唆を与えます。日本では入国審査や在留資格の更新時に重点が置かれており、税金や社会保険料の納付状況などが重要視されています。ただし、アメリカのようにSNSや日常の行動まで監視する体制は導入されていません。
しかし、少子高齢化で外国人労働者の受け入れが進む日本では、将来的に「継続的審査」に近い制度が検討される可能性があります。そのときに備え、在留外国人ができることは明確です。まず、税金や社会保険料を含む法令順守を徹底することです。小さな怠慢が大きなリスクにつながることを理解する必要があります。
次に、SNSでの行動に注意を払うことです。日本では常時チェック制度は一般化していませんが、公開情報として判断材料にされる可能性はあります。過激な投稿や誤解を招く表現は避けるべきです。さらに、地域社会と信頼関係を築くことも重要です。地域に溶け込み、周囲との関係を良好に保つことは、自身を守る力になります。
制度が厳格化した場合に備えて、行政書士など専門家に相談できる体制を持つことも有効です。制度が複雑になったときに、専門的な助言や手続の支援を得られる環境があることは安心材料になります。
これからの在留外国人に求められる姿勢
アメリカの事例は、治安維持に効果的である一方で自由やプライバシーとのバランスを問うものです。日本も今後、外国人受け入れを拡大する中で、同様の制度に近づく可能性があります。そのときに備えて、在留外国人に求められるのは日常的に法令を守り、社会と責任ある関わりを持つ姿勢です。
制度が変わることを恐れるのではなく、自分の行動を整えることで安心して暮らせる基盤を作ることができます。これからの時代、在留外国人には適応力と社会参加の姿勢がより強く求められているのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。