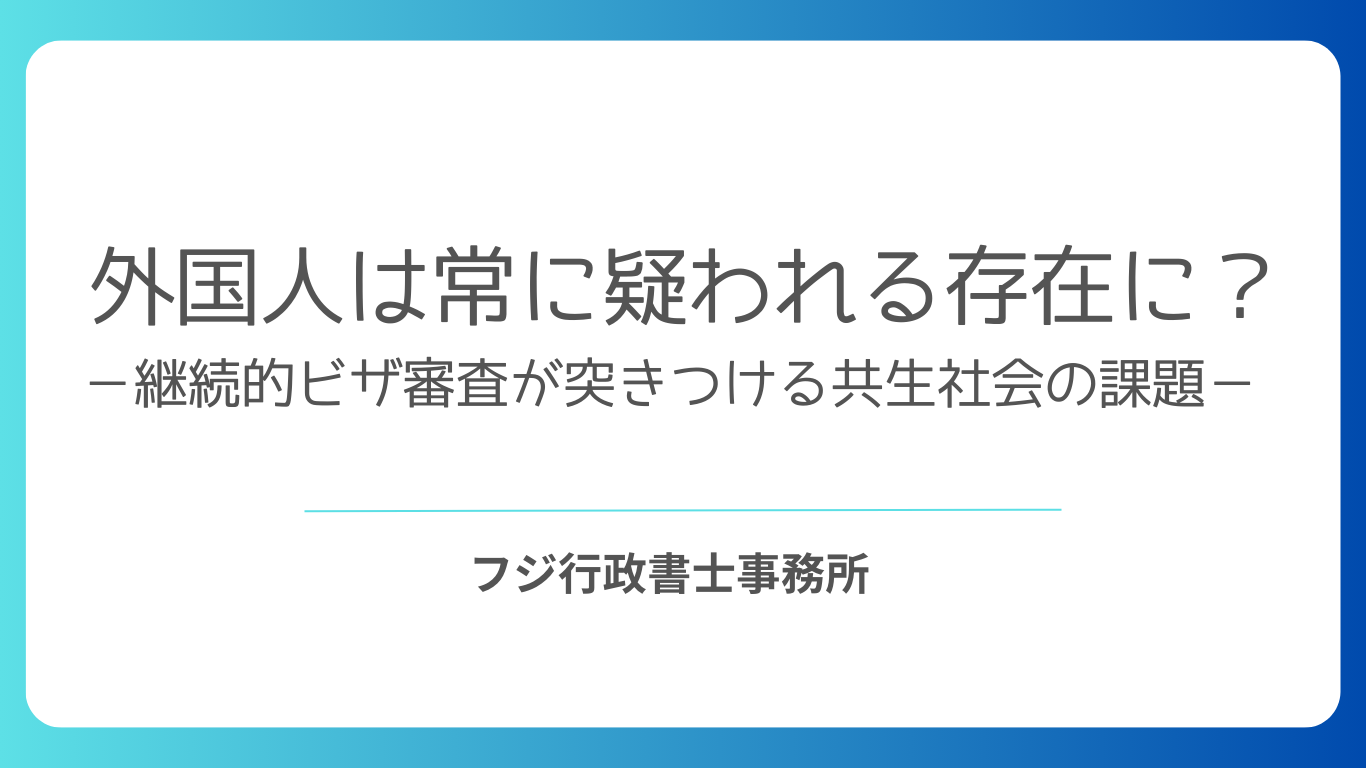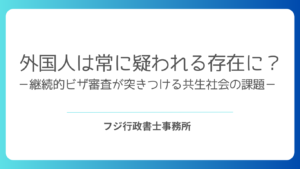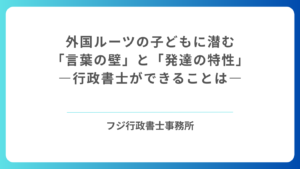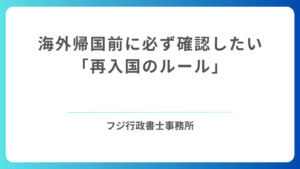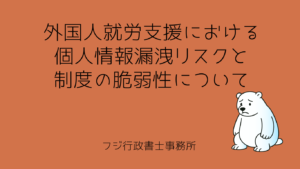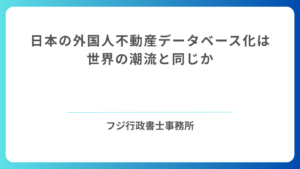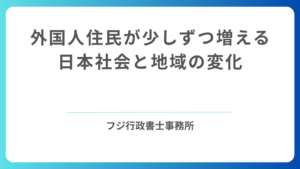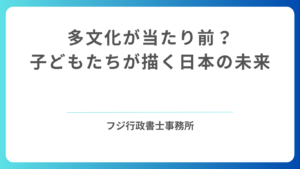監視が生む安心と不安――アメリカの新制度の二面性
アメリカ政府が導入を進めている「継続的審査」は、外国人管理のあり方を大きく変えるものです。従来はビザ取得後は比較的安定した滞在が可能と考えられてきましたが、新制度では入国後も常に監視されることになります。
この仕組みは治安維持や不法滞在防止に効果的で、犯罪やテロのリスクを早期に発見できると期待されています。国民に安心を与える制度として支持されやすい面もあります。
一方で、監視の対象が外国人であることから「常に疑われている」という意識を強めます。外国人自身は「信用されていない存在」と感じやすく、周囲からも監視対象として見られ孤立感や不安が生じるのです。安心をもたらす制度が同時に不安も生むという二面性を抱えています。
公平性の名の下に起きる「国籍フィルター」
制度は表向き全員平等に適用されると説明されますが、実務上は国籍によって厳しさに差が出る可能性があります。安全保障上懸念のある国の出身者は厳格に、経済や政治で関係の深い国の出身者は緩やかに扱われる、といった傾向が起きやすいのです。
この「国籍フィルター」は、本人の行動に関わらず差別を固定化します。特定国出身というだけで疑われやすくなり、雇用や教育、住居の場面で「その国の人はリスクがある」という偏見が広がりかねません。制度が公平性を欠くと、差別を正当化する温床になってしまいます。
さらに一度「国籍による監視」が強化されると、社会に深く染み込みやすいのが厄介な点です。採用や契約の現場で「国籍だけで線引き」が常態化すれば、差別は日常生活の中で正当化され、改善が難しくなります。
日常生活に現れる新しい差別のかたち
監視体制は外国人の日常にも影響します。就職では「ビザが取り消されやすい」と考えられ、採用を避けられる可能性があります。住居探しでは「トラブルを招くかも」と判断され、契約を断られる例も増えるでしょう。教育現場では、子どもが「監視対象の家庭」と見なされ偏見にさらされる恐れがあります。
SNSでの発言が誤解されることも大きなリスクです。文化や言語の違いから冗談や不満が過激な思想とみなされ、自由な発言が制限されかねません。こうした「目に見えにくい差別」は日常の中に浸透し、外国人が社会に溶け込みにくくする要因となります。
差別の影響は本人だけでなく、家族や次世代にも及びます。子どもが学校や地域社会で偏見を受ければ、アイデンティティの形成や教育機会にも悪影響が及びます。監視制度は安全を守るはずのものですが、家族ごと「潜在的に危険」と見なされるならば、共生社会の基盤そのものを揺るがすことになりかねません。
共生社会を守るために必要な視点
差別を防ぐためには、まず制度の透明性が必要です。違反とされる基準を明確にすることで不安や偏見を抑えられます。次に実効的な公平性が欠かせません。国籍ではなく、行動や生活実態に基づいて判断される仕組みが求められます。
さらに、外国人自身の声を制度設計に反映させることが重要です。当事者の意見を取り入れることで不公平感を減らし、制度への理解が深まります。そして、受け入れる社会全体の意識も問われます。外国人を「リスク要因」ではなく共に暮らす仲間として認める姿勢が不可欠です。
日本にとってもこれは遠い話ではありません。すでに在留資格更新では納税や社会保険加入の有無が重視され、出身国によって追加書類が多いなどの声もあります。今後アメリカ型の監視制度が参考にされれば、同じ課題が浮上するでしょう。だからこそ今のうちから「差別を制度が助長しない」仕組みを意識しておく必要があります。
アメリカの制度は治安維持に有効である一方で、新たな差別を生み出す危険もはらんでいます。安全と共生をどう両立させるか――それは日本社会にとっても喫緊の課題なのです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。