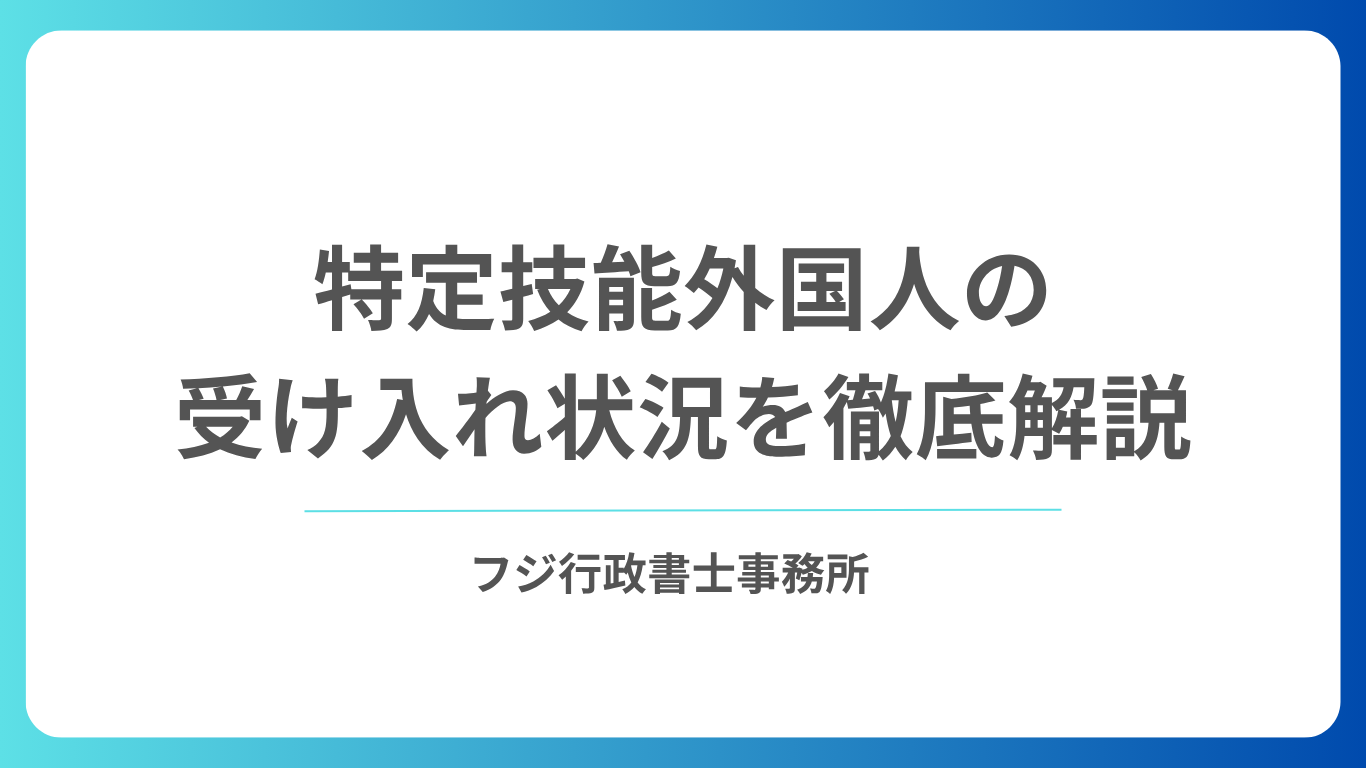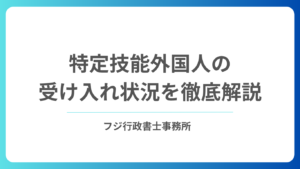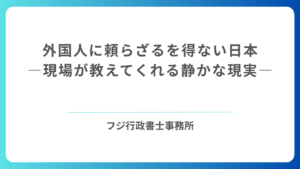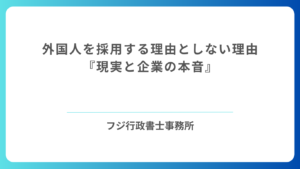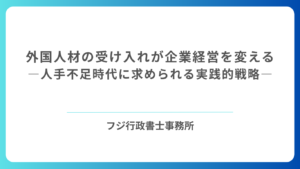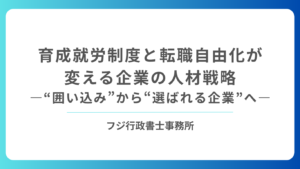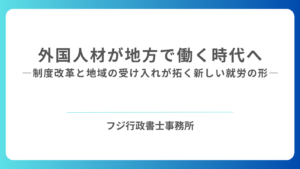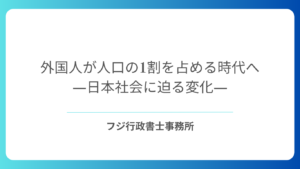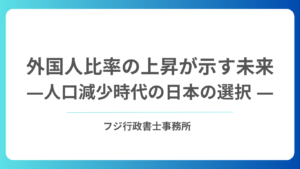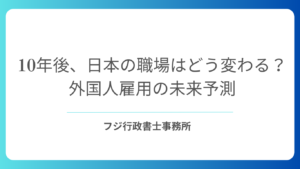地域別に見る特定技能外国人の受け入れ現場
「特定技能」制度の導入により、これまで技能実習制度に依存してきた現場にも変化が現れている。いまや外国人労働者は、単なる「労働力」ではなく、地域の産業と暮らしを支える欠かせない存在となりつつある。
たとえば北海道では、農業・畜産の分野で外国人材の存在が定着しつつある。季節労働に適した制度として特定技能が選ばれ、現地の自治体も通訳や生活ガイドの提供に取り組んでいる。九州では食品加工業や水産加工業での人手不足に対応すべく、特定技能による人材登用が進み、企業と行政の連携による生活支援も見られるようになってきた。
一方、長野県や富山県などの内陸部では、製造業や宿泊業での需要が高く、生活インフラが整っていない地域では民間団体が主導するサポート体制が重要になっている。介護分野においては、全国的に外国人材への依存度が増しており、特に東北や中国地方では、日本人のなり手不足を補う存在として歓迎されている。
都市部と地方の特定技能外国人受け入れ課題
東京・大阪・名古屋といった大都市圏では、介護・建設・外食・清掃など多種多様な分野で外国人が活躍している。人口規模や産業の集中により外国人の数も多く、外国人受け入れの「最前線」と言える。
ただし都市部ならではの課題もある。たとえば、日本語能力に差がある人が多いにもかかわらず、企業側が十分な教育体制を整えていないケースや、生活支援の情報が自治体や地域によってばらついている問題などが指摘されている。
特定技能制度では原則として一定レベルの日本語能力と技能試験の合格が求められるが、実際の職場ではコミュニケーションの困難から孤立してしまうケースもある。都市部は物価や家賃も高く、生活に余裕がない外国人が多いため、労働条件だけでなく「生活インフラの充実」が今後の大きな課題といえる。
特定技能制度を支える地域社会と企業の取り組み
特定技能制度の運用は、制度設計以上に「地域の受け入れ姿勢」に大きく左右される。国が定める最低限の要件を超えて、どこまで丁寧な支援を地域で構築できるかが、外国人が安心して暮らし、働き続けられるかどうかの分かれ目となる。
具体的には、自治体による多言語対応窓口の設置や、NPO・ボランティア団体による日本語教室、地域住民との交流イベントなどが好例だ。たとえば埼玉県川口市では、市役所と地域団体が連携し、外国人労働者の相談会を定期的に開催している。こうした取り組みが、外国人の孤立を防ぎ、トラブルの未然防止にもつながっている。
また、企業側の理解も不可欠である。労働力不足を補うために外国人を雇うだけではなく、長期的に「共に働く仲間」として受け入れる姿勢が求められている。企業の内部研修、日本語教育の補助、住居の提供など、民間主導でできることも多い。
いまや特定技能制度は一部の地域だけの話ではない。全国の自治体・企業・地域住民が、それぞれの立場で「共に生きる社会」をどうつくるか。その取り組み一つひとつが、日本社会全体の成熟を映す鏡となっている。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。