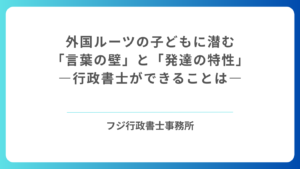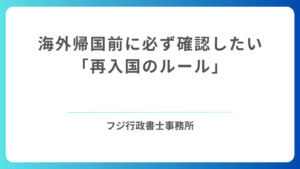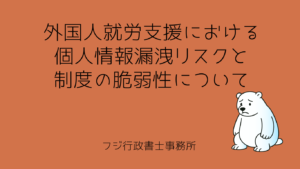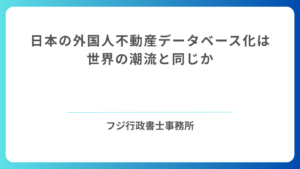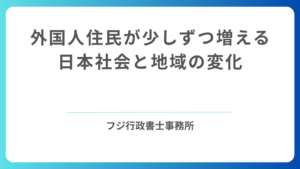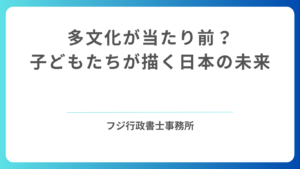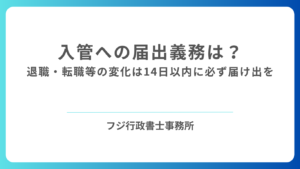ノルウェーの手厚い支援と進む少子化
ノルウェーは、育児休業制度や保育環境の整備が極めて充実している国の一つです。夫婦で合計1年間の育児休業が取得でき、父親にも一定期間の取得義務があります。また、保育所の利用も平等に開かれており、待機児童の問題もほとんど見られません。かつては高水準の出生率を誇っていましたが、近年では少子化の波を免れることができず、出生率は人口維持に必要とされる水準を下回るまでに落ち込んでいます。
制度面では世界的に見ても非常に恵まれているノルウェーにおいて、なぜ出生率の低下が進んでいるのでしょうか。その背景には、社会の価値観の変化があります。ノルウェーでは男女平等が進み、女性が自らのキャリアを優先する選択をすることが増えています。また、「子どもを持たない」という選択肢が人生の一形態として受け入れられるようになり、子育てが「当然のもの」ではなくなってきたのです。
さらに、生活費や住宅費の高騰も、子どもを持つことへの心理的・経済的ハードルを押し上げています。制度が整っていても、それを活用できる「余裕」や「意欲」がなければ、出生にはつながりません。出生率の低下は単なる経済的問題ではなく、価値観やライフスタイルの多様化によるものだという見方が主流になっています。
世界に広がる共通課題と一部の成功例
日本もまた同様の状況にあります。少子化対策として育児休業制度の拡充や保育料の無償化、こども家庭庁の創設などの取り組みが行われていますが、出生率は1.2前後と依然として低水準です。日本の場合、長時間労働や性別役割分担、キャリアと子育ての両立困難といった構造的問題が複雑に絡み合い、制度の恩恵を十分に享受できない人が多いのが現実です。
このような現象は、ノルウェーや日本に限らず、韓国、ドイツ、イタリアなど多くの先進国で共通して見られます。特に韓国では、教育費の高騰や競争社会の中で、若者の間に「結婚しない」「子どもを持たない」という意識が強く、出生率は1.0を切るほどにまで低下しています。
一方で、フランスやスウェーデンのように比較的高い出生率を維持している国もあります。これらの国では、保育と仕事の両立を支援するだけでなく、事実婚や多様な家族形態を受け入れる柔軟な制度設計と社会的な寛容性が一定の効果を上げているとされています。
制度整備の先にある「選ばれる社会」へ
では、少子化に歯止めをかける打開策はあるのでしょうか。制度の充実だけでなく、社会全体の価値観や生き方の多様性をどう支えるかが、鍵となるでしょう。出産や子育てを「推奨」するだけでなく、それを選ぶ人が躊躇なく人生設計に組み込めるような柔軟な働き方、生活の安定、そして育児とキャリアの両立可能な社会構造が求められます。
また、男性の家庭進出の推進や、育児にかかわる時間と責任を男女が平等に分担する文化の醸成も不可欠です。ノルウェーでは既に父親の育児参加が当たり前となっていますが、それでも「産むかどうか」の選択は個々人の価値観に委ねられています。ゆえに、支援を拡充することと並行して、「産み育てることが魅力的で持続可能な人生の選択肢である」と感じられるような社会的メッセージの発信が、今後ますます重要になっていくでしょう。
少子化は止められるのか――。答えは一つではありませんが、少なくとも「制度の整備が全てを解決する」という幻想を捨て、社会全体で人々の多様な生き方を支える覚悟と仕組みが問われていることは、間違いありません。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。