ハンガリーの大胆な少子化対策とその狙い
ハンガリーでは、2010年代以降、政府が少子化を国家的課題と捉え、住宅・経済面での手厚い子育て支援を矢継ぎ早に導入してきました。代表的な施策の一つが、18歳から40歳までの既婚女性を対象とした無利子ローンと出産による返済免除の制度です。第一子が生まれると返済猶予、第二子で元本の一部免除、第三子の誕生で残りの返済が全額免除される仕組みとなっています。
さらに、3人以上の子どもを持つ家庭には新築・中古住宅の購入を支援する補助金や、低金利ローンが提供されます。住宅取得時の税金減免や、4人以上の子を持つ母親に対する所得税の生涯免除といった制度も設けられました。中でも注目されたのが「7人乗り車購入補助金」で、多子世帯の生活を具体的に支える狙いがうかがえます。
これらの施策は、子育て世帯の経済的不安を軽減するという点では高く評価され、導入当初は一時的に出生率の上昇につながる成果も見られました。2011年に1.23だった合計特殊出生率は、2019年には1.55にまで上昇し、「経済的支援によって出生率は改善できる」という見方に一定の説得力を与える結果となりました。
政策の限界と再び進む少子化
しかし、2020年以降の状況を見ると、出生率は再び低下傾向にあります。物価上昇やエネルギー価格の高騰、インフレなどが家計を直撃し、出産や子育てに慎重になる家庭が増えたためです。また、都市部を中心に若者の国外移住やライフスタイルの変化が進み、結婚や出産を選ばない層が拡大しています。たとえ経済的インセンティブが魅力的であっても、「子どもを持つこと自体が人生の理想ではない」とする価値観が広がる中では、政策の効果にも限界があることが浮き彫りになりました。
このように、ハンガリーの事例は「金銭的支援=出生率上昇」という単純な因果関係が成立しないことを示しています。子どもを持つことが、経済的にだけでなく、社会的・文化的にも「安心で魅力的」と感じられる環境がなければ、持続的な効果は得られません。制度の厚さだけでは、価値観や将来不安といった無形の障壁を乗り越えることは難しいのです。
これは日本や韓国にとっても大きな示唆を与えます。両国とも少子化が深刻化する中で、保育料の無償化や出産一時金の拡充といった経済的支援策が講じられていますが、出生率の改善には結びついていません。長時間労働、育児とキャリアの両立困難、ジェンダー役割の固定観念といった構造的課題を解決しなければ、支援の効果は限定的なものにとどまってしまうでしょう。
人口が増える国との決定的な違いとは
一方で、世界には人口が今なお増加している国々があります。代表例がインド、フィリピン、ナイジェリアといった新興国です。これらの国では、若年人口の比率が高く、結婚や出産が早期に行われる文化が根強く残っています。子どもを持つことが「人生の自然な流れ」として社会的に支えられており、また、家族や地域コミュニティのつながりが子育てを後押ししています。
もちろん、こうした国々では経済的には不安定な面も多く、教育機会や女性のキャリア保障といった課題も抱えています。それでも出生率が高い背景には、「子を持つことへの社会的肯定感」と「子育てをめぐる価値観の共有」が強く作用していることが挙げられます。
逆に言えば、成熟した先進国においては、経済支援や制度整備だけでなく、「文化的・精神的な土台」の再構築が求められているのです。誰もが安心して子どもを持てる、そして育てることが喜びや誇りとして感じられる社会。そこにこそ、少子化克服の本質的なカギがあるのかもしれません。
ハンガリーの教訓は、支援策の厚さではなく、その「受け手がどう感じるか」が重要であることを、静かに私たちに語りかけています。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。


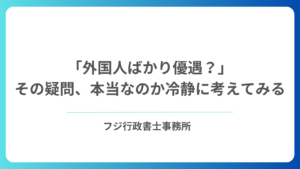


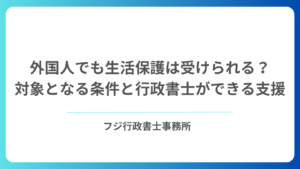




コメント