地元に戸惑いも――外国人による不動産購入がもたらす影響
近年、全国各地で外国人による不動産購入が増えています。都市部の高級マンションだけでなく、観光地の宿泊施設、温泉街の旅館、さらには地方の空き家や山林など、さまざまな不動産が外国人投資家の手に渡るようになっています。こうした動きに対して、地域によっては経済活性化や空き家解消の一助として肯定的に受け止める声もある一方、実際にその土地で暮らす住民の間では困惑や不安の声も少なくありません。
たとえば、所有者が外国に在住しているため、建物の管理が不十分になったり、災害時に連絡がつかないといった事態が発生しています。また、用途がはっきりしないまま購入され放置された空き地や施設が、地域の景観や治安に悪影響を及ぼすケースもあります。誰が所有しているのかすら分からない状態に、住民は不信感や無力感を抱くこともあります。
法的には適正な取引であっても、地域社会においては「買われた側」の心情や不安が置き去りにされがちです。その結果、住民の間で「もう地域は自分たちの手を離れたのでは」という感覚が芽生え、無関心やあきらめへとつながるリスクもあります。
摩擦と共存――生活文化の違いとすれ違い
特に観光地やリゾートエリアでは、外国人オーナーによる短期滞在型の運用が増え、地域の生活リズムに変化が生じています。別荘として数年に一度しか使われない物件や、バケーションレンタルとして頻繁に人が出入りする住宅などが増えることで、近隣住民との接点が薄れ、トラブルのリスクも高まります。
たとえば、ゴミの分別ルールが守られない、騒音が夜遅くまで続く、敷地境界を越えて駐車される――こうした小さな摩擦が積み重なり、「外国人=迷惑」といった偏見や誤解が生まれる土壌にもなりかねません。また、地元の伝統や習慣に理解がないまま土地が使われることで、文化的な断絶が顕在化する場面もあります。
一方で、外国人側も「地域にどう関わってよいのかわからない」「言葉が通じず孤立している」と感じていることが少なくありません。トラブルの背景には、互いの無理解や情報不足があるのです。
このような状況において求められるのは、排除や規制ではなく、共に暮らすための「対話」と「橋渡し」の工夫です。例えば自治体が多言語での生活ガイドや地域ルールを案内したり、地元の住民団体が新しいオーナーを歓迎する小さな集いを開いたりすることで、互いの距離を縮めることができます。外国人を「一時的な所有者」ではなく、「地域の一員」として迎える姿勢こそが、真の共生への一歩となるはずです。
「誰が買うか」ではなく「どう関わるか」が問われている
日本では、外国人による不動産購入を一律に制限する法律はなく、憲法で保障された財産権や国際的な投資協定に基づき、外国籍の人でも土地や建物を自由に取得できます。しかし、その自由が拡大する一方で、購入された地域の側が感じる「不可視の負担」は見過ごされがちです。
とりわけ、人口減少が進む地方では、空き家を売却できること自体が歓迎される反面、「誰に売るのか」「どんな使われ方をするのか」によって地域の風景や人間関係が大きく変わることがあります。「買ってくれたから感謝すべき」という声の裏で、「こんな形で地域が変わってしまうとは」という複雑な感情が交錯するのが現実です。
これからの社会に必要なのは、「外国人が買える・買えない」という制度論だけではなく、「購入後、どう関わり合っていけるか」を地域ごとに考える仕組みです。所有情報の可視化、利用目的の共有、地域への説明責任――これらをルール化することで、地域の安心感は大きく変わるはずです。
そして何より重要なのは、「外国人=外から来た人」ではなく、「同じ地域で共に暮らす人」としての視点を持つことです。トラブルの芽を早期に摘み取り、誤解を丁寧に解きほぐし、信頼関係を築いていく努力が、未来の共生社会を支えていく鍵になるでしょう。購入される側の声に耳を傾け、共に暮らす姿勢を築くことこそが、これからの日本の地域にとって最も本質的な課題なのかもしれません。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。


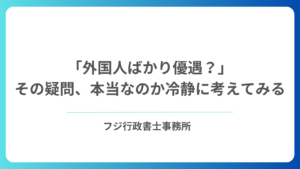


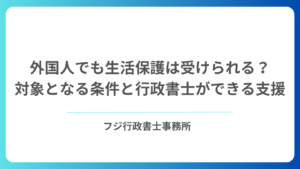




コメント