COEが不交付になってしまったとき、どうすればいい?
在留資格認定証明書(COE)が不交付になると、申請者やその家族にとって大きなショックです。せっかく準備して提出した書類が受理されず、「なぜ許可が出なかったのか」「次にどうすれば良いのか」が分からず、不安に陥る方も少なくありません。
しかし、COEが不交付になったからといって、すべてが終わりではありません。状況を冷静に整理し、正しいステップを踏めば、再申請によって許可を得ることは可能です。
不交付通知だけでは理由は分からない?
COEが不交付となった場合、出入国在留管理局からは「不交付通知書」が発行されます。しかしこの通知には、「申請人が在留資格該当性を満たしていないと判断したため」といった簡潔な記載しかないことが多く、具体的に何が問題だったのかは書かれていません。
そのため、通知書を読むだけでは理由が特定できないのが現実です。このような曖昧な通知に戸惑う方も多く、「次にどこを改善すれば良いのか分からない」と感じるのは無理もありません。
この場合、入管の運用では原則として本人が一度だけ窓口で不交付理由を聞くことができるとされています。ただし、どのような対応をしてくれるかは担当官の裁量により異なるため、事前に準備を整え、できれば行政書士など専門家の同行を検討すると安心です。
再申請を成功させるには、原因の特定と修正がカギ
同じ内容で再申請しても、結果が覆る可能性は低いとされています。そのため、再申請では不交付の原因を正確に把握し、その上で書類の見直しや説明の補強を行うことが不可欠です。
たとえば、以下のような点がチェックされます:
- 提出書類の不備(翻訳漏れ、証明書の内容不整合、古い情報など)
- 経歴や在留歴に問題がある(過去のオーバーステイ、虚偽申告歴など)
- 受け入れ機関(企業・学校など)の信頼性や安定性
- 計画の整合性(雇用契約や留学計画の現実性)
こうした点のどこに問題があったのかを入管からのヒアリングや経験に基づいて把握し、「再提出書類」「補足説明書」「陳述書」などを用いて根拠を明確にした申請を行うことで、許可が出る可能性は大きく改善します。
不交付後の再申請は、心理的にも時間的にも負担が大きいものです。そのうえで再び結果を得るには、「どこが問題だったのか」「どうすれば改善できるのか」を冷静に見極め、論理的に再構成された書類を揃えることが成功への近道となります。
特に、本人が申請理由をうまく説明できない、または日本語での手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家と一緒に対応することで、入管とのやりとりや再申請の戦略がスムーズに進むことが多いです。
まとめ:再申請は「根拠の修正」がすべて
COEが不交付になったからといって、すぐにあきらめる必要はありません。ただし、ただ再提出するだけでは結果は変わりません。不交付通知書の内容を読み解き、入管でのヒアリングを通じて原因を把握し、 不足点や誤解を生んだ点をしっかり補足して再申請することが重要です。
不交付の経験は決して無駄ではなく、再申請のための学びとして活かすことができます。不安な場合は、経験豊富な専門家とともに、再スタートを切る準備をしていきましょう。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。


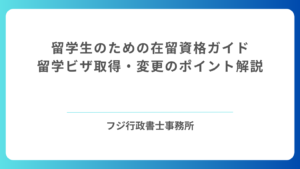
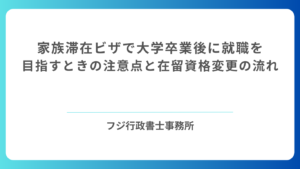
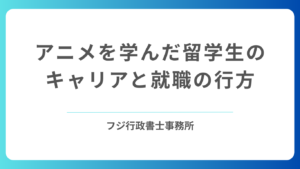
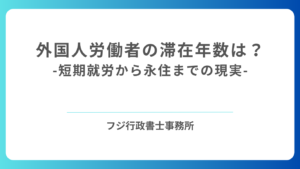
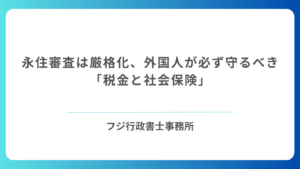
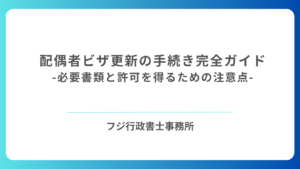
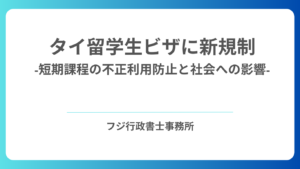
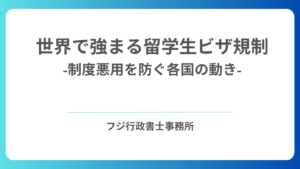
コメント